2009年04月27日
保護者会(ゆとり教育編)
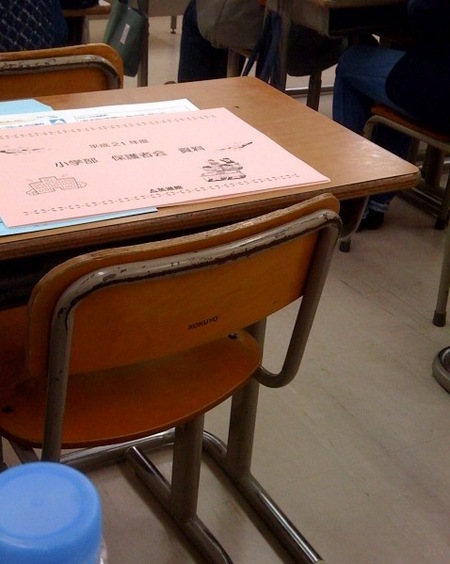
昨日は、あかりが通う某塾の保護者会に参加してきました。あかりは、昨年から某塾のテスト会員(テストのみ受ける)になり、今年からは、週2回通っています。まだ小学4年生なのですが、強制的に通わせているわけではなく、本人が行きたい・楽しいということで通わせています。。。
塾側からは、
・算数や、国語の学習方法についてのアドバイス
・今回唐津に新設される早稲田系列校の情報提供
などが行われましたが、一番のメインは、今回実施される「新学習指導要領」についてです。いわゆる「ゆとり教育」からの脱却ですね。我々が小学校・中学校の頃によくいわれていた「詰め込み教育」「受験戦争」「偏差値主義」による弊害(校内暴力、いじめ、登校拒否など)を改善するためにに、生きるために必要な力の育成が必要ということで、ゆとり教育が始まったようです。
詳細はこちら
今回の保護者会で話を聞いて初めて知ったのが、我々が子供の頃受けたカリキュラムに対し、今の子供達が受けているそれの「量(質はわかりません)」が、ほぼ半分だということです。
おおまかですが、
我々の小学校・中学校時代(昭和40~50年代)を100とすると、
昭和55~60年くらいにゆとり教育がはじまり、カリキュラムの量が約70(3割減)に
更に、平成10年くらいにさらに「ゆとり」に傾き、更に3割減に
つまり、0.7(3割減)×0.7(3割減)=0.49→ほぼ半分
になっているとのことでした。そもそもゆとり教育に国の教育方針を変更するにあたり、問題意識・目的があったのでしょう。効果もあったと思います。しかし、内容・質はともかく、量が半分だと、そもそも「やばいんじゃない?」と思うのは私だけでしょうか?
何事も、最低源必要な量があると思います。そのあたりを官僚のみなさまは理解できなかったのでしょうか?
このような方針変更で、一番影響を受けるのは、いたいけな子供達です。
そういえば、私が高校生のときにも同様なことがありましたね。私はいわゆる共通一次(試験)世代なのですが、我々が一年生のときに、理科に理科Ⅰ、社会に現代社会という科目が新設されました(今はないんじゃないかな?)。つまり、大学受験をする際に、初めてその科目を受験する学年だったのです(笑)。正直嫌でしたし、かわいそうなのが、私達の一学年上で、浪人された方々です。内容は理科Ⅰ、現代社会共、旧カリキュラムより平易だといわれていましたが、学んだこともない科目を受験するのは大変です。
そのような経験をした世代が、今、国の施策立案の実務を担っていらっしゃるはずですので、是非このような経験を施策に反映してほしいと思った次第です。
あかりは、「ふーん」とあまり興味がないようですが(笑)。
Posted by 坂本 剛 at 08:31│Comments(0)
│今日の出来事






