2011年02月21日
第85回綾水会(一区切り編)
今年に入り、いろんな案件が頭の中をめぐり、ちと発散状態に陥っております。
そろそろ、私と一緒に新規事業を担当するスタッフを雇用しないといけない状態になってきたかな?と感じています。ご興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。
その懸案の一つであった先週2月15日の綾水会は、昨年9月に、綾尾さん、水口さんが一線から退かれるということを発表されたのに伴い、区切りの会として数年ぶりに<拡大>して開催しました。

第一回目から数えて、85回目の開催です。基本的には毎月第2火曜日に開催しています。業務等の都合で、開催日をずらしたことはありますが、約7年間、毎月欠かさず開催してきました。
当初は、メインプレゼンターを探すだけでも苦労しましたが、今ではドタバタしつつもなんとかラインナップはできるようになりましたね。先日、今までの資料を整理していて、メインプレゼン、ショートプレゼンターのリストを作ってみたら、我ながらよくやってきたなーと思った次第です。
そのあたりのことは、以前産学官連携ジャーナルに寄稿した文章がありますのでご参照ください。
今回は<拡大>ということで、私が東京出張の際に色々お世話になっている
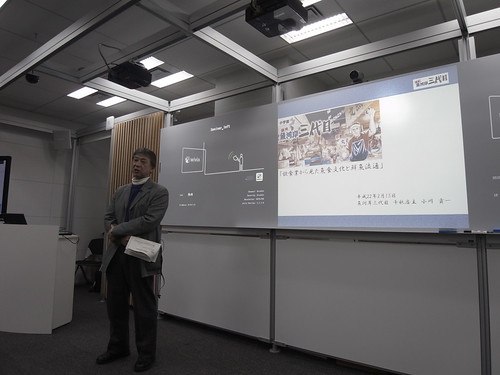
築地魚河岸三代目千秋の店主である小川貢一氏に「飲食業から見た魚食文化 と鮮魚流通」といったテーマで基調講演していただきました。一次産業に対する地域活性については、農業関係の活性化の話はよくあるのですが、漁業関係になるとあまり話を聞きません。日本の食文化の大きな特徴の一つは<魚食>の文化です。私自身、子供の頃は<お子ちゃま系>の食べ物ばかりだったのですが、今では<魚中心>の食生活を行っています(というか、太郎源と千秋が中心の食生活?)。

引き続き、メインプレゼンは、日本IBMの社内ベンチャー(新規事業)のコンペを勝ち抜き、現在事業化を目指しているビジネスプラン「スマートな鮮魚流通シス テム"Internet of Fish"」 を、日本アイ・ビー・エム株式会社グローバル・ビジネス・サービス事業 バリューネット事業開発部長の久保田 和孝 氏に、小川さんと同様東京からお越しいただきプレゼンしていただきました。
ICTを活用し、地域と大消費地(大都市圏等)を結びつけることにより、地域資産の一つである「鮮魚」の流通を活性化させ、地域活性化につなげて いくといった内容です。

いわゆる<クラウド>のインフラをIBMが提供し、その上で地域と消費地、顧客を関係づけていくというビジネスモデルです。
既に北海道では実証実験を行われており、今後九州でも同様の実証実験~ビジネス展開を検討されています。課題は色々あると思いますが、北海道に続き、九州でも実証実験ができればいいなと思っています。
個人的には、ターゲットを国内ではなく、アジアに絞ってビジネスプランを構築したら面白い収益モデルが構築できるのではないかと思った次第です。
メインプレゼン終了後は、水口さんと綾尾さんにご挨拶をいただきました。
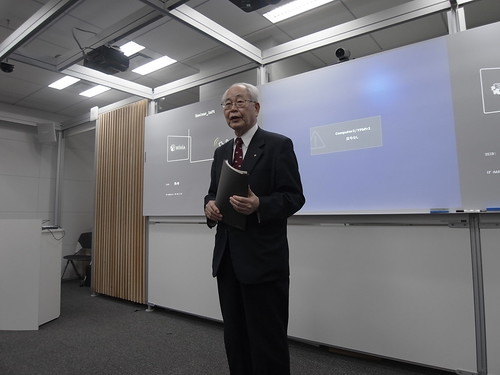
水口さんは、今まで地域のいろんな役回りをお引き受けになっていらっしゃったのですが、今年以降は、順に役職を引き継ぎされていかれるようです。地域発のVC<KVP>の経営者として我々のネットワークを支援していただきました。本当にありがとうございました。
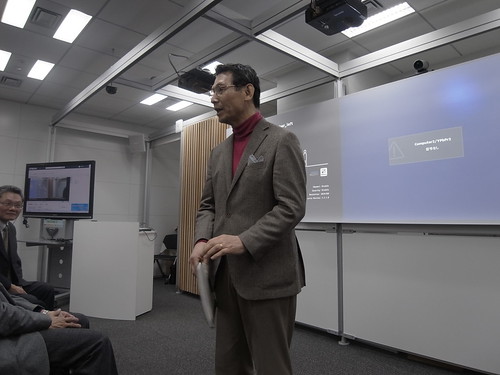
綾尾さんには、綾水会だけでなく、九大のアドバイザー、客員教授として、今まで九大発の事業化案件のサポートをしていただいてきました。綾尾さんご自身、今年は<お父様の没後50年><出身であるMITの創立150年><九大の創立100年>と、いろんなAnniversaryが重なっていらっしゃるようで、今回<綾水会7年>という随想録を執筆されました。これは綾水会メンバー限定です。
お二人に共通するのは<誠実さ><謙虚さ>です。とりわけベンチャー関係だと、それらが軽んじられる傾向にありますが、ハイテクであれローテクであれ、グローバルであれドメスティックであれ商売の原点として非常に重要なことだと思います。この7年お二人から学んだことを肝に、今後も綾水会を継続していく所存です。

最後は、記念品贈呈。長浜さんが選んでくれたアートフラワー。

いつもポーズで撮ろうとしたら、某ウザイ人に制止され、3人で記念撮影をパチリ。

ネットワークは、今回100名近い方が参加されたということで、こんな感じで内田洋行さんの2Fかごった返し状態でした。。。
で、<今後綾水会って名前はどうなるんですか?>ということを質問されます。。。
ほぼ新しい名前は決まっているのですが、これはまた改めて発表させていただきますね(笑)。
そろそろ、私と一緒に新規事業を担当するスタッフを雇用しないといけない状態になってきたかな?と感じています。ご興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。
その懸案の一つであった先週2月15日の綾水会は、昨年9月に、綾尾さん、水口さんが一線から退かれるということを発表されたのに伴い、区切りの会として数年ぶりに<拡大>して開催しました。

第一回目から数えて、85回目の開催です。基本的には毎月第2火曜日に開催しています。業務等の都合で、開催日をずらしたことはありますが、約7年間、毎月欠かさず開催してきました。
当初は、メインプレゼンターを探すだけでも苦労しましたが、今ではドタバタしつつもなんとかラインナップはできるようになりましたね。先日、今までの資料を整理していて、メインプレゼン、ショートプレゼンターのリストを作ってみたら、我ながらよくやってきたなーと思った次第です。
そのあたりのことは、以前産学官連携ジャーナルに寄稿した文章がありますのでご参照ください。
今回は<拡大>ということで、私が東京出張の際に色々お世話になっている
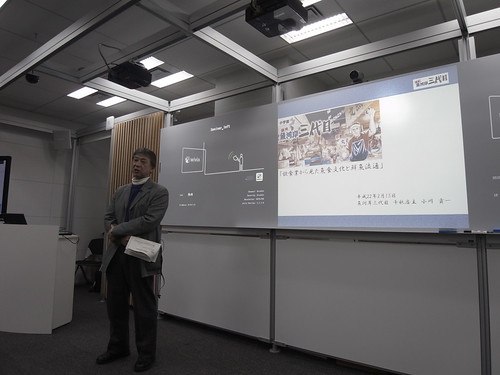
築地魚河岸三代目千秋の店主である小川貢一氏に「飲食業から見た魚食文化 と鮮魚流通」といったテーマで基調講演していただきました。一次産業に対する地域活性については、農業関係の活性化の話はよくあるのですが、漁業関係になるとあまり話を聞きません。日本の食文化の大きな特徴の一つは<魚食>の文化です。私自身、子供の頃は<お子ちゃま系>の食べ物ばかりだったのですが、今では<魚中心>の食生活を行っています(というか、太郎源と千秋が中心の食生活?)。

引き続き、メインプレゼンは、日本IBMの社内ベンチャー(新規事業)のコンペを勝ち抜き、現在事業化を目指しているビジネスプラン「スマートな鮮魚流通シス テム"Internet of Fish"」 を、日本アイ・ビー・エム株式会社グローバル・ビジネス・サービス事業 バリューネット事業開発部長の久保田 和孝 氏に、小川さんと同様東京からお越しいただきプレゼンしていただきました。
ICTを活用し、地域と大消費地(大都市圏等)を結びつけることにより、地域資産の一つである「鮮魚」の流通を活性化させ、地域活性化につなげて いくといった内容です。

いわゆる<クラウド>のインフラをIBMが提供し、その上で地域と消費地、顧客を関係づけていくというビジネスモデルです。
既に北海道では実証実験を行われており、今後九州でも同様の実証実験~ビジネス展開を検討されています。課題は色々あると思いますが、北海道に続き、九州でも実証実験ができればいいなと思っています。
個人的には、ターゲットを国内ではなく、アジアに絞ってビジネスプランを構築したら面白い収益モデルが構築できるのではないかと思った次第です。
メインプレゼン終了後は、水口さんと綾尾さんにご挨拶をいただきました。
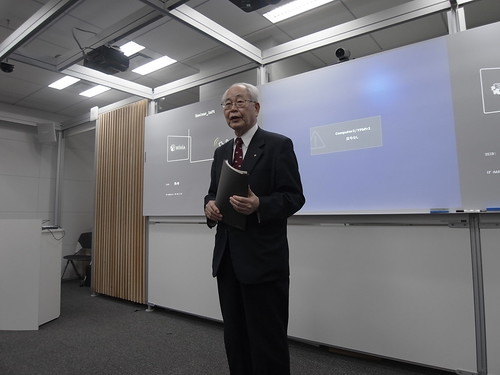
水口さんは、今まで地域のいろんな役回りをお引き受けになっていらっしゃったのですが、今年以降は、順に役職を引き継ぎされていかれるようです。地域発のVC<KVP>の経営者として我々のネットワークを支援していただきました。本当にありがとうございました。
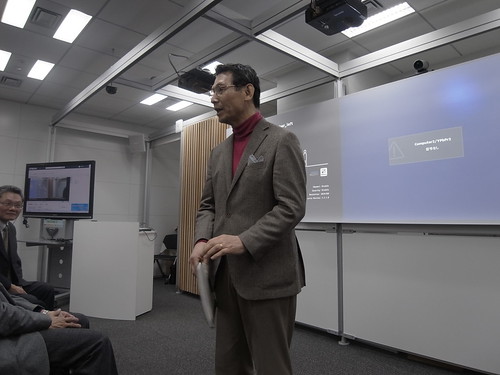
綾尾さんには、綾水会だけでなく、九大のアドバイザー、客員教授として、今まで九大発の事業化案件のサポートをしていただいてきました。綾尾さんご自身、今年は<お父様の没後50年><出身であるMITの創立150年><九大の創立100年>と、いろんなAnniversaryが重なっていらっしゃるようで、今回<綾水会7年>という随想録を執筆されました。これは綾水会メンバー限定です。
お二人に共通するのは<誠実さ><謙虚さ>です。とりわけベンチャー関係だと、それらが軽んじられる傾向にありますが、ハイテクであれローテクであれ、グローバルであれドメスティックであれ商売の原点として非常に重要なことだと思います。この7年お二人から学んだことを肝に、今後も綾水会を継続していく所存です。

最後は、記念品贈呈。長浜さんが選んでくれたアートフラワー。

いつもポーズで撮ろうとしたら、某ウザイ人に制止され、3人で記念撮影をパチリ。

ネットワークは、今回100名近い方が参加されたということで、こんな感じで内田洋行さんの2Fかごった返し状態でした。。。
で、<今後綾水会って名前はどうなるんですか?>ということを質問されます。。。
ほぼ新しい名前は決まっているのですが、これはまた改めて発表させていただきますね(笑)。
Posted by 坂本 剛 at 07:59│Comments(1)
│大学発ベンチャー支援
この記事へのコメント
煩悶を忘れるわけではない彼が氏の悩みは彼に対してあまり重く、悔しい。
Posted by Air Jordan Fusion 3 at 2011年02月22日 11:28










