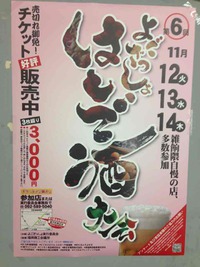2009年01月26日
第3回九州ナレッジ交流会(その2)
九州ナレッジ交流会の続きです・・・

石村萬盛堂の石村社長のご講演が終了し、グループ討議へ・・・
今回の九州ナレッジ交流会のケーステーマは、
○知識活用について
○場の設計・活用
○組織を超えたネットワークづくり
の三つです。知識活用については、
○TOTOの知的財産本部から小島さんが「知的活用をお客様満足につなげる~事業に貢献する知的財産活動~」
場の設計・活用については、
○日立ハイテクノロジーの佐藤さんが「那珂事業所における知識経営と場創り〈もの創りのためのワークプレイス創りの実践〉」
○東芝 セミコンダクター社の川又さんが「想いを繋げる-場-の設計について 社内の知識創造活動「CAKE(ケイク)」ご紹介」
といったテーマでケース発表を行いました。
そして、最後に組織を超えたネットワークづくりについては、
○モノづくり連携大賞 受賞活動における産学連携の取り組みについて
といったテーマで私がケース発表を行いました。


TOTOさんのプレゼンでは、知的財産の創出と業績評価の関係、技術の新陳代謝といったところが印象的でした。TOTOは、人材育成・評価においてダブルラダーを採用しているようです。いわゆる昇級段階においてマネジメント人材と専門人材に分かれるのですが、技術の専門社員と一般社員の知的財産創出(特許の出願等)では相関が見られるとのことです。また、入社年次ごとの知的財産創出のデータ分析を動的に行っています。入社年次、入社してから時間(勤務年数)ごとにどれだけ知的創造活動を行っているかなどの分析は非常に興味深いものでした。


東芝に川又さんは、IDM(垂直統合型半導体メーカー:Integrated Device Manufacturer)として必要な組織横断的な「場)作り「CAKE(Community Activity of Knowledge Engineering)」についてプレゼンを行いました。取り組みを社内で認知してもらう、継続してもらうためにメルマガを発行するなど地道な取り組みをされているようです。
日立ハイテクノロジーズの佐藤さんは、那珂事業所で行っているワークプレイスの実践例、ビジネス顕微鏡を利用した組織診断などについてプレゼンされました。日立グループの企業が、知識創造プロセス、いわゆるSECIモデルを回すための場の形成を支援するために、ワークプレイスをあそこまで突っ込んで実践しているということに非常に驚きました。中小・ベンチャー企業にとてはある意味脅威ですね。
そして、最後に私がモノづくり連携大賞を事例として九州大学における産学連携の取り組みについて発表させていただきました。重点を置いたのは「ネットワーク形成の重要性」。

上記のスライドのような感じでまとめさせていただきました。
キーポイントは、
人=知識である
いい人のネットワークはいいネットワーク(信頼のネットワーク、信頼のネットワークの自浄作用)
目的をもったネットワーク
Give and take ⇒Giveが先(情報取りだけは・・・)
オープンマインド&ネットワークリテラシーの重要性といったところです。
いくらナレッジマネジメントシステムが発達しても、コアなナレッジは人の頭、気持ちの中にある。つまり、知識共有=人との交流が基本である。
自分にとって有益な人、信頼のおける人から紹介してもらった人はほぼ信頼のおける人である。なぜなら、変&怪しい人を紹介してしまと、紹介した本人自体の信頼が損なわれてしまい、ネットワークから弾き出されてしまう。変&怪しい人を紹介することはリスクなのである。
情報を集めたければ、まず、自分が情報を発信することが重要である。また、言葉の通りGiveが先、Takeは後である。take take(タケタケ)族は嫌われ、信頼のネットワークの中では生きて行くことができず淘汰されていく・・・
自分が人的ネットワーク形成において今まで培った知識をちょっとだけオープンにさせていただきました。
以上、非常に内容が濃い交流会だったので、あっという間に終わってしまいました(笑)。

交流会終了後には懇親会が開催されました。


左の写真は、沖電気の堀田さん。九大工学部OBで、私とほぼ年齢も一緒。同じ時期に学生時代を過ごしたので、工学部ネタで盛り上がりました。
右の写真は、日立ハイテクノロジーズの佐藤さん。ビジネス顕微鏡、ワークプレイスなど先進的な知識経営についての取り組みを実践されています。

最後は、福太郎の樋口君が「博多一本締め~十日恵比寿バージョン~」で締めを行いました。
半日でしたが非常に知的好奇心をくすぐられる素晴しいイベントでした。主催の富士ゼロックスさん、協力の九電さん、ありがとうございました。是非このような活動を九州で継続してくださいね。

石村萬盛堂の石村社長のご講演が終了し、グループ討議へ・・・
今回の九州ナレッジ交流会のケーステーマは、
○知識活用について
○場の設計・活用
○組織を超えたネットワークづくり
の三つです。知識活用については、
○TOTOの知的財産本部から小島さんが「知的活用をお客様満足につなげる~事業に貢献する知的財産活動~」
場の設計・活用については、
○日立ハイテクノロジーの佐藤さんが「那珂事業所における知識経営と場創り〈もの創りのためのワークプレイス創りの実践〉」
○東芝 セミコンダクター社の川又さんが「想いを繋げる-場-の設計について 社内の知識創造活動「CAKE(ケイク)」ご紹介」
といったテーマでケース発表を行いました。
そして、最後に組織を超えたネットワークづくりについては、
○モノづくり連携大賞 受賞活動における産学連携の取り組みについて
といったテーマで私がケース発表を行いました。


TOTOさんのプレゼンでは、知的財産の創出と業績評価の関係、技術の新陳代謝といったところが印象的でした。TOTOは、人材育成・評価においてダブルラダーを採用しているようです。いわゆる昇級段階においてマネジメント人材と専門人材に分かれるのですが、技術の専門社員と一般社員の知的財産創出(特許の出願等)では相関が見られるとのことです。また、入社年次ごとの知的財産創出のデータ分析を動的に行っています。入社年次、入社してから時間(勤務年数)ごとにどれだけ知的創造活動を行っているかなどの分析は非常に興味深いものでした。


東芝に川又さんは、IDM(垂直統合型半導体メーカー:Integrated Device Manufacturer)として必要な組織横断的な「場)作り「CAKE(Community Activity of Knowledge Engineering)」についてプレゼンを行いました。取り組みを社内で認知してもらう、継続してもらうためにメルマガを発行するなど地道な取り組みをされているようです。
日立ハイテクノロジーズの佐藤さんは、那珂事業所で行っているワークプレイスの実践例、ビジネス顕微鏡を利用した組織診断などについてプレゼンされました。日立グループの企業が、知識創造プロセス、いわゆるSECIモデルを回すための場の形成を支援するために、ワークプレイスをあそこまで突っ込んで実践しているということに非常に驚きました。中小・ベンチャー企業にとてはある意味脅威ですね。
そして、最後に私がモノづくり連携大賞を事例として九州大学における産学連携の取り組みについて発表させていただきました。重点を置いたのは「ネットワーク形成の重要性」。
上記のスライドのような感じでまとめさせていただきました。
キーポイントは、
人=知識である
いい人のネットワークはいいネットワーク(信頼のネットワーク、信頼のネットワークの自浄作用)
目的をもったネットワーク
Give and take ⇒Giveが先(情報取りだけは・・・)
オープンマインド&ネットワークリテラシーの重要性といったところです。
いくらナレッジマネジメントシステムが発達しても、コアなナレッジは人の頭、気持ちの中にある。つまり、知識共有=人との交流が基本である。
自分にとって有益な人、信頼のおける人から紹介してもらった人はほぼ信頼のおける人である。なぜなら、変&怪しい人を紹介してしまと、紹介した本人自体の信頼が損なわれてしまい、ネットワークから弾き出されてしまう。変&怪しい人を紹介することはリスクなのである。
情報を集めたければ、まず、自分が情報を発信することが重要である。また、言葉の通りGiveが先、Takeは後である。take take(タケタケ)族は嫌われ、信頼のネットワークの中では生きて行くことができず淘汰されていく・・・
自分が人的ネットワーク形成において今まで培った知識をちょっとだけオープンにさせていただきました。
以上、非常に内容が濃い交流会だったので、あっという間に終わってしまいました(笑)。

交流会終了後には懇親会が開催されました。


左の写真は、沖電気の堀田さん。九大工学部OBで、私とほぼ年齢も一緒。同じ時期に学生時代を過ごしたので、工学部ネタで盛り上がりました。
右の写真は、日立ハイテクノロジーズの佐藤さん。ビジネス顕微鏡、ワークプレイスなど先進的な知識経営についての取り組みを実践されています。

最後は、福太郎の樋口君が「博多一本締め~十日恵比寿バージョン~」で締めを行いました。
半日でしたが非常に知的好奇心をくすぐられる素晴しいイベントでした。主催の富士ゼロックスさん、協力の九電さん、ありがとうございました。是非このような活動を九州で継続してくださいね。
唐津市と九大の共同研究成果「完全養殖のマサバ」が試験出荷開始らしい
ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??
福岡での人の流れ調査実験
明けましておめでとうございます(午年編)
都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」
九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)
ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??
福岡での人の流れ調査実験
明けましておめでとうございます(午年編)
都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」
九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)
Posted by 坂本 剛 at 08:27│Comments(0)
│産学連携