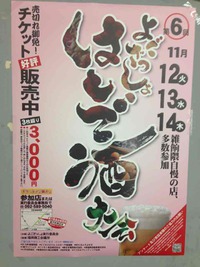2010年11月11日
味覚センサー的な太郎源の宴
今週月曜日(11月8日)に、筑波大学から産学連携関係のヒアリングということで、池田さんが来学されました。
私は都合が合わず、ヒアリング自体には参加できませんでしたが、夜の食事に同席させていただきました。

場所は、太郎源本店。相変わらず美味なお刺身盛り合わせです。
そこで、池田さんに見せていただいたのが、

筑波大学のブランドグッズ「桐の華」。
桐の花酵母を使って造った吟醸酒です。桐の葉は、筑波大学の校章(九大は松)。
その場で、試飲させていただきましたが、非常にすっきりとした味わいでした。
そんなこんなで、話題がお酒の話に拡がっていったのですが、乾杯のビールの後、以前キープしていた焼酎を出してもらったら、同じく宴に参加された都甲先生(システム情報科学研究院長)が一言、
「坂本さん、流石ですね~明るい農村をお飲みとは~」
「えっなぜですか?」とお聞きすると、「明るい農村」と、ブランド焼酎として有名な「森伊蔵」は、味覚的にほぼ一緒だとおっしゃるのです。森伊蔵といえば、ネットでも一升瓶で数万円する超ブランド焼酎です。
都甲先生といえば、味覚センサーの発明者。味覚センサーの事業化を行ったベンチャー「INSENT」のHPはこちら
また、都甲先生は、味覚センサーを引っさげて、NTV「世界で一番受けたい授業」に三度、NHK「爆笑問題のニッポンの教養」に出演されたことがある九大の名物教授です。
味については、いろんな考え方がありますが、少なくとも我々人間が舌で感じる「味覚」について、味覚センサーで分析すると「明るい農村」は、「森伊蔵」とデータ的にかなり似ている、つまりほぼ同じ味覚だということでした。金額はかなり異なりますけどね(笑)。
私自身、特に細かく考えておらず、以前「明るい農村」を別のお店で飲んだ際に飲みやすかったので、太郎源でもキープしていたのでした。私の「味覚」も学術的に評価された?かも?
お酒は嗜好品なので、味覚のデータだけでなく、ブランディング、イメージなどトータルで商品の価値が決まりますので、一概に味が「明るい農村」=「森伊蔵」とはなりませんが、ある客観的指標において
、ほぼ同じデータを示すということは事実です。
参考までに、都甲先生の著書『ハイブリッド・レシピ』p. 153に焼酎の味覚について以下の文章があります。
++++++++++++++
焼酎
さあ、10年前から人気急上昇の焼酎です。さすが、鹿児島、宮崎といった九州に産地が集中していますね。その味を甘味と苦味で見てみました。なお、ここでの苦味はコーヒーやゴーヤの苦味と違い、コクの原因ともなる味であり、日本酒や焼酎では隠し味として重要な味です。これがないと、スッキリしすぎ、もの足りない味となり、おいしくありません。
誰もが知っている米焼酎の白岳、麦焼酎のいいちこ、芋焼酎の黒霧島、さつま島美人、吉兆宝山、一刻者、富乃宝山、明るい農村と勢ぞろいです。
米焼酎は甘味と苦味をもち、クセのない豊かな味と言えるでしょう。麦焼酎は、米焼酎と芋焼酎の中間に位置し、まろやかな味を特徴とします。焼酎ブームを起こした下町のナポレオンこと「いいちこ」もここです。興味深いことに、芋焼酎である富乃宝山が麦焼酎と同じ領域に位置しています。
芋焼酎は3つに分類できそうです。フルーティタイプ、バランスタイプ、コク・キレ味タイプの3つです。近年とみに人気の出た「明るい農村」は、芳醇な香りと軽やかかつリッチな味をもっています。宮崎の生んだ芸術品「黒霧島」、鹿児島で最も飲まれている焼酎と言われる「さつま島美人」は柔らかですっきりとした味が楽しめる逸品です。
甘味と苦味がほどよくバランスした「一刻者」「吉兆宝山」「さつま木挽」は、まろやかで上品な味わいを特徴とします。
ロック、水割り、お湯割りといかようにも楽しめる焼酎、これがまた焼酎の人気を支えている要因でしょう。その場の雰囲気で、またそのときの気分で、バリエーション豊富な焼酎から、未知の一品を選ぶのも、また新たな感激に巡り合えるチャンスかもしれません。
++++++++++++++
都甲先生、いろいろご教示いただきありがとうございました!
と、そんなことをしているうちに、当日お仕事で来福されていた@nobiさんからtwitter経由で、太郎源に知り合いといってみたいというご要望が・・・太郎源広報部長として、急遽新別館を予約。

そのやりとりをしてる間に、気がつくと目の前に @nobiさん御一行が(笑)。twitterとリアルが交差する面白い体験をした次第です。
最後に、都甲先生からいただいた焼酎のグルーピングマップを貼り付けておきます。皆さんが普段飲んでいる焼酎が、味覚センサーによってどんな分類をされているか?結構面白いですよ。

私は都合が合わず、ヒアリング自体には参加できませんでしたが、夜の食事に同席させていただきました。

場所は、太郎源本店。相変わらず美味なお刺身盛り合わせです。
そこで、池田さんに見せていただいたのが、

筑波大学のブランドグッズ「桐の華」。
桐の花酵母を使って造った吟醸酒です。桐の葉は、筑波大学の校章(九大は松)。
その場で、試飲させていただきましたが、非常にすっきりとした味わいでした。
そんなこんなで、話題がお酒の話に拡がっていったのですが、乾杯のビールの後、以前キープしていた焼酎を出してもらったら、同じく宴に参加された都甲先生(システム情報科学研究院長)が一言、
「坂本さん、流石ですね~明るい農村をお飲みとは~」
「えっなぜですか?」とお聞きすると、「明るい農村」と、ブランド焼酎として有名な「森伊蔵」は、味覚的にほぼ一緒だとおっしゃるのです。森伊蔵といえば、ネットでも一升瓶で数万円する超ブランド焼酎です。
都甲先生といえば、味覚センサーの発明者。味覚センサーの事業化を行ったベンチャー「INSENT」のHPはこちら
また、都甲先生は、味覚センサーを引っさげて、NTV「世界で一番受けたい授業」に三度、NHK「爆笑問題のニッポンの教養」に出演されたことがある九大の名物教授です。
味については、いろんな考え方がありますが、少なくとも我々人間が舌で感じる「味覚」について、味覚センサーで分析すると「明るい農村」は、「森伊蔵」とデータ的にかなり似ている、つまりほぼ同じ味覚だということでした。金額はかなり異なりますけどね(笑)。
私自身、特に細かく考えておらず、以前「明るい農村」を別のお店で飲んだ際に飲みやすかったので、太郎源でもキープしていたのでした。私の「味覚」も学術的に評価された?かも?
お酒は嗜好品なので、味覚のデータだけでなく、ブランディング、イメージなどトータルで商品の価値が決まりますので、一概に味が「明るい農村」=「森伊蔵」とはなりませんが、ある客観的指標において
、ほぼ同じデータを示すということは事実です。
参考までに、都甲先生の著書『ハイブリッド・レシピ』p. 153に焼酎の味覚について以下の文章があります。
++++++++++++++
焼酎
さあ、10年前から人気急上昇の焼酎です。さすが、鹿児島、宮崎といった九州に産地が集中していますね。その味を甘味と苦味で見てみました。なお、ここでの苦味はコーヒーやゴーヤの苦味と違い、コクの原因ともなる味であり、日本酒や焼酎では隠し味として重要な味です。これがないと、スッキリしすぎ、もの足りない味となり、おいしくありません。
誰もが知っている米焼酎の白岳、麦焼酎のいいちこ、芋焼酎の黒霧島、さつま島美人、吉兆宝山、一刻者、富乃宝山、明るい農村と勢ぞろいです。
米焼酎は甘味と苦味をもち、クセのない豊かな味と言えるでしょう。麦焼酎は、米焼酎と芋焼酎の中間に位置し、まろやかな味を特徴とします。焼酎ブームを起こした下町のナポレオンこと「いいちこ」もここです。興味深いことに、芋焼酎である富乃宝山が麦焼酎と同じ領域に位置しています。
芋焼酎は3つに分類できそうです。フルーティタイプ、バランスタイプ、コク・キレ味タイプの3つです。近年とみに人気の出た「明るい農村」は、芳醇な香りと軽やかかつリッチな味をもっています。宮崎の生んだ芸術品「黒霧島」、鹿児島で最も飲まれている焼酎と言われる「さつま島美人」は柔らかですっきりとした味が楽しめる逸品です。
甘味と苦味がほどよくバランスした「一刻者」「吉兆宝山」「さつま木挽」は、まろやかで上品な味わいを特徴とします。
ロック、水割り、お湯割りといかようにも楽しめる焼酎、これがまた焼酎の人気を支えている要因でしょう。その場の雰囲気で、またそのときの気分で、バリエーション豊富な焼酎から、未知の一品を選ぶのも、また新たな感激に巡り合えるチャンスかもしれません。
++++++++++++++
都甲先生、いろいろご教示いただきありがとうございました!
と、そんなことをしているうちに、当日お仕事で来福されていた@nobiさんからtwitter経由で、太郎源に知り合いといってみたいというご要望が・・・太郎源広報部長として、急遽新別館を予約。

そのやりとりをしてる間に、気がつくと目の前に @nobiさん御一行が(笑)。twitterとリアルが交差する面白い体験をした次第です。
最後に、都甲先生からいただいた焼酎のグルーピングマップを貼り付けておきます。皆さんが普段飲んでいる焼酎が、味覚センサーによってどんな分類をされているか?結構面白いですよ。

唐津市と九大の共同研究成果「完全養殖のマサバ」が試験出荷開始らしい
ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??
福岡での人の流れ調査実験
明けましておめでとうございます(午年編)
都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」
九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)
ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??
福岡での人の流れ調査実験
明けましておめでとうございます(午年編)
都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」
九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)
Posted by 坂本 剛 at 20:47│Comments(0)
│産学連携