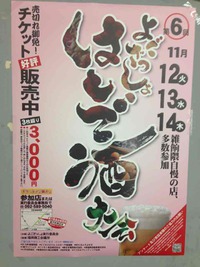2010年11月13日
そこが知りたい「産学官連携」の最新事情
先日ブログで告知していた第6回中小企業産学官連携推進フォーラム「そこが知りたい『産学官連携』の最新事情」が、11月10日に東京ビッグサイトで開催されました。

「産」「学」「官」からパネラーが集まりディスカッションを行うといった形式です。私は、技術移転機関関係なのですが、3までもポジション(九大知財本部)つながりの話でしたので、「学」の立場での参加です。
パネラーは、
神奈川科学技術アカデミー(KAST) 理事長
馬来 義弘 氏
(株)産学連携機構九州 代表取締役社長
坂本 剛 氏
タカノ(株) 相談役
堀井 朝運 氏
(独)国立高等専門学校機構
富山高等専門学校 専攻科 准教授
袋布 昌幹 氏
そして、当日午前中に表彰式が開催された第5回モノづくり連携大賞「大賞」受賞者である
㈱日本ステントテクノロジー 代表取締役社長
山下 修蔵 氏
コーディネーターは、
(独)中小企業基盤整備機構 新事業支援部
統括インキュベーションマネージャー
加藤 英司
といったメンバーでした。自己紹介の後、まずは「産」の立場からのプレゼンテーション
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<日本ステントテクノロジー山下さんのプレゼンについて>
ハイテクの開発には、ローテク(ものづくり、マネジメント)基盤技術が重要
新規事業の開発は「見極め力」と「経営者の本気」から
岡山での医療機器関係の産業集積が非常によかった
山下さんは、60歳過ぎてからの大学発ベンチャー起業(これはすごい!:元化学系メーカー)
<タカノ堀井さんのプレゼンについて>
某メーカーの100%下請け企業
先代社長から10年社長をやってほしいと言われた
社長就任後、6年で一部上場
新規事業⇒大学を頼るしかなかった
中小企業⇒単なる技術移転だけではうまくいかない
新規事業、産学連携のポイントは「人材育成」
誘発型新規事業開発
新規事業開発のコンセプトは、顧客ニーズを良く調査し、事業(商品)を、顧客のために具体的な形にするための戦略的な思考である
新規事業に必要なファンクション⇒「事業開発」「技術開発」「知財開発」
続いて「学」の立場からのプレゼンテーション
<富山高専袋布(タフ)さんのプレゼンについて>
開発は「学」の主導だった~高専には、マジメに・ノビノビやれる土壌がある
高専の役割:地域産業に貢献すること(法律で条文化されているとのこと)
「産学官連携」は技術ではなく、プレゼンスで売る
「出来上がった技術」は、もう、買ってくれない
私のプレゼンは、割愛させていただきます(笑)。
最後に「官」の立場で、
<KAST馬来さんのプレゼンについて>
神奈川県R&Dネットワーク構想
かながわ産学公連携推進協議会
公的支援機関を有効活用すると投資効率(研究開発費)が高い!
中小機構の積極的活用のすすめ~中小機構「太鼓論」:大きく叩けば大きく響く
支援企業はお客様(「支援してあげる」のではなく「支援させていただく」)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
私自身、普段お会いしない方々からの体験談・事例等を聴くことができ、非常に勉強になりました。
中でも、タカノの堀井さんのお話は、中小企業の「下請けスパイラル」を経験したことがある私にとって、非常に感銘を受ける話でした。
某企業の100%下請け会社の経営を任され、わずか6年で上場。そのドライビングフォースが「産学連携」を活用した新規事業開発だったのです。
その成功の鍵となったのが「人材育成」。新たなプロジェクトには、必ず社員を参加させたそうです。
その結果、今では社員の中から博士号を取得した方も現れています。
私自身、福岡の中小企業で働いている際に、下請けから脱却できないかと新商品を開発したり、新たな生産体制の構築したりといろんなことにチャレンジし、結果たどりついたのが「大学」。
私は、大学と近づいているうちに、ミイラ取りがミイラになってしまったのですが、堀井さんは、日本の中小企業がチャレンジしながら、中々実現できない「下請けからの脱却」「上場」という夢を実現されていらっしゃるのです。
しかも、60歳を過ぎて、早稲田大学ビジネススクールに入学されMBAを取得。さらに修士論文を先生と共著で「実践中小企業の新規事業開発―町工場から上場企業への飛躍」という本にまとめられていらっしゃいます。
いやはや脱帽するしかありませんね(笑)。非常に機知に富んだパネルディスカッションでした。
そして、夜に向かったのは築地。そこでサプライズが待っていたのでした・・・

「産」「学」「官」からパネラーが集まりディスカッションを行うといった形式です。私は、技術移転機関関係なのですが、3までもポジション(九大知財本部)つながりの話でしたので、「学」の立場での参加です。
パネラーは、
神奈川科学技術アカデミー(KAST) 理事長
馬来 義弘 氏
(株)産学連携機構九州 代表取締役社長
坂本 剛 氏
タカノ(株) 相談役
堀井 朝運 氏
(独)国立高等専門学校機構
富山高等専門学校 専攻科 准教授
袋布 昌幹 氏
そして、当日午前中に表彰式が開催された第5回モノづくり連携大賞「大賞」受賞者である
㈱日本ステントテクノロジー 代表取締役社長
山下 修蔵 氏
コーディネーターは、
(独)中小企業基盤整備機構 新事業支援部
統括インキュベーションマネージャー
加藤 英司
といったメンバーでした。自己紹介の後、まずは「産」の立場からのプレゼンテーション
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<日本ステントテクノロジー山下さんのプレゼンについて>
ハイテクの開発には、ローテク(ものづくり、マネジメント)基盤技術が重要
新規事業の開発は「見極め力」と「経営者の本気」から
岡山での医療機器関係の産業集積が非常によかった
山下さんは、60歳過ぎてからの大学発ベンチャー起業(これはすごい!:元化学系メーカー)
<タカノ堀井さんのプレゼンについて>
某メーカーの100%下請け企業
先代社長から10年社長をやってほしいと言われた
社長就任後、6年で一部上場
新規事業⇒大学を頼るしかなかった
中小企業⇒単なる技術移転だけではうまくいかない
新規事業、産学連携のポイントは「人材育成」
誘発型新規事業開発
新規事業開発のコンセプトは、顧客ニーズを良く調査し、事業(商品)を、顧客のために具体的な形にするための戦略的な思考である
新規事業に必要なファンクション⇒「事業開発」「技術開発」「知財開発」
続いて「学」の立場からのプレゼンテーション
<富山高専袋布(タフ)さんのプレゼンについて>
開発は「学」の主導だった~高専には、マジメに・ノビノビやれる土壌がある
高専の役割:地域産業に貢献すること(法律で条文化されているとのこと)
「産学官連携」は技術ではなく、プレゼンスで売る
「出来上がった技術」は、もう、買ってくれない
私のプレゼンは、割愛させていただきます(笑)。
最後に「官」の立場で、
<KAST馬来さんのプレゼンについて>
神奈川県R&Dネットワーク構想
かながわ産学公連携推進協議会
公的支援機関を有効活用すると投資効率(研究開発費)が高い!
中小機構の積極的活用のすすめ~中小機構「太鼓論」:大きく叩けば大きく響く
支援企業はお客様(「支援してあげる」のではなく「支援させていただく」)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
私自身、普段お会いしない方々からの体験談・事例等を聴くことができ、非常に勉強になりました。
中でも、タカノの堀井さんのお話は、中小企業の「下請けスパイラル」を経験したことがある私にとって、非常に感銘を受ける話でした。
某企業の100%下請け会社の経営を任され、わずか6年で上場。そのドライビングフォースが「産学連携」を活用した新規事業開発だったのです。
その成功の鍵となったのが「人材育成」。新たなプロジェクトには、必ず社員を参加させたそうです。
その結果、今では社員の中から博士号を取得した方も現れています。
私自身、福岡の中小企業で働いている際に、下請けから脱却できないかと新商品を開発したり、新たな生産体制の構築したりといろんなことにチャレンジし、結果たどりついたのが「大学」。
私は、大学と近づいているうちに、ミイラ取りがミイラになってしまったのですが、堀井さんは、日本の中小企業がチャレンジしながら、中々実現できない「下請けからの脱却」「上場」という夢を実現されていらっしゃるのです。
しかも、60歳を過ぎて、早稲田大学ビジネススクールに入学されMBAを取得。さらに修士論文を先生と共著で「実践中小企業の新規事業開発―町工場から上場企業への飛躍」という本にまとめられていらっしゃいます。
いやはや脱帽するしかありませんね(笑)。非常に機知に富んだパネルディスカッションでした。
そして、夜に向かったのは築地。そこでサプライズが待っていたのでした・・・
唐津市と九大の共同研究成果「完全養殖のマサバ」が試験出荷開始らしい
ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??
福岡での人の流れ調査実験
明けましておめでとうございます(午年編)
都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」
九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)
ブログタイトル変更(2回目)→産学連携的な??
福岡での人の流れ調査実験
明けましておめでとうございます(午年編)
都市情報誌「fU+(エフ・ユー プラス)」
九州経済フォーラム忘年会(植物工場編)
Posted by 坂本 剛 at 11:51│Comments(1)
│産学連携
この記事へのコメント
先日のフォーラム,御世話になりました。
堀井さんの話は私にとっても大変刺激的でした!
またこれを機会にお近づきになれれば...と思っています。
これからもご指導いただければ幸いです!
堀井さんの話は私にとっても大変刺激的でした!
またこれを機会にお近づきになれれば...と思っています。
これからもご指導いただければ幸いです!
Posted by たふ@富山高専 at 2010年11月14日 19:43