2014年03月20日
福岡タワー25年、私も社会人25年
今週月曜日(3月17日)は、東京に出張していました。
翌日18日に事務所へ出社してみると、机の上に、

福岡タワーを模したリーフレットが置かれていました。
3月17日に「福岡タワー25周年記念新イルミネーション点灯式」が開催されたようです。
そうなんですよね。福岡タワーができて25年経つんですよね。
福岡タワーは、1989年に百道浜で開催された「アジア太平洋博覧会」のシンボルタワーとして建設されたものです。
タワーの高さは「234メートル」。中腹あたりに展望レストランがあるのですが、そこの高さが123メートルです。
1989年といえば、私が大学を卒業した年です。つまり、私の社会人生活をスタートした年に出来上がったので、福岡タワーの歴史は、私の社会人キャリアの歴史と時期が一致するのです。そういった意味でなんだか感慨深い気分になりました。私もなんだかんだと4半世紀働いているということになります。。。

お祝いの品として、紅白饅頭も頂きました。ちなみに、このお饅頭は、ホワイトデー発案で有名な石村萬盛堂製です。
25周年を記念して、17日以降新しいイルミネーションが始まるみたいですよ。百道浜近辺を夕方以降通過される方、訪問される方、乞うご期待です。
翌日18日に事務所へ出社してみると、机の上に、

福岡タワーを模したリーフレットが置かれていました。
3月17日に「福岡タワー25周年記念新イルミネーション点灯式」が開催されたようです。
そうなんですよね。福岡タワーができて25年経つんですよね。
福岡タワーは、1989年に百道浜で開催された「アジア太平洋博覧会」のシンボルタワーとして建設されたものです。
タワーの高さは「234メートル」。中腹あたりに展望レストランがあるのですが、そこの高さが123メートルです。
1989年といえば、私が大学を卒業した年です。つまり、私の社会人生活をスタートした年に出来上がったので、福岡タワーの歴史は、私の社会人キャリアの歴史と時期が一致するのです。そういった意味でなんだか感慨深い気分になりました。私もなんだかんだと4半世紀働いているということになります。。。

お祝いの品として、紅白饅頭も頂きました。ちなみに、このお饅頭は、ホワイトデー発案で有名な石村萬盛堂製です。
25周年を記念して、17日以降新しいイルミネーションが始まるみたいですよ。百道浜近辺を夕方以降通過される方、訪問される方、乞うご期待です。
タグ :福岡タワー
2014年03月14日
初めての緊急地震速報受信
本日、深夜2時に、ご存知のとおり愛媛で震度5強(マグニチュード6.1)の地震が発生しました。
私は、福岡市在住ですが、その時間寝ていて、突然アラーム音で目が覚めました。そして『なんの音?』と寝ぼけながら考えようと思った瞬間に、家が揺れ始めました。揺れは数十秒で収まりましたが、このレベルの揺れは、6年前のこの時期(3月)に発生した福岡県西方沖地震以来でした。当時のほうが揺れはひどかったですけどね。
その後の報道で、軽傷者は出た模様ですが大きな被害ななくてホッとしています。一方、今回初めての経験だったのが「緊急地震速報」の受信でした。
そうです、あのアラーム音は、私のスマホが受信した「緊急地震速報」だったのです。ドコモによると(私のスマホはソフトバンクですが、、、)
緊急地震速報は、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に素早くお知らせするものです。
ドコモでは、気象庁から配信された 「一般向け緊急地震速報」を利用して最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)の地域(全国を約200の地域に区分)の携帯電話に一斉配信いたします。
とあります。寝ぼけていたので、記憶が曖昧ですが、私の場合、アラーム音で目が覚めてすぐに揺れが始まったのではないかと思います。
また、緊急地震速報を受信したということは、私が住んでいる場所で震度4以上を記録したということにもなります。
そんな揺れる直前に警報が届いても、、、とお考えの方もいるかもしれませんが、今回の経験から「ギリギリでも緊急速報」を受信したほうが、その後の対応にはいいのではいかと思った次第です。
少なくとも、寝た状態より、目覚めて意識があったほうが、室内での落下物への対応など、被害を回避する行動を取れる可能性が高いはずですもんね。
巨大地震の発生が噂される日本で、地震を避けること、事前に予測することは事実上不可能です。そのためには、地震が発生した場合の初期対応を如何に行うかが重要になってくると思います。そういった意味で、今回の緊急地震速報は、程度の差はあれどある一定の効果はあったのではないかと思いました。
まあ、あまり受信したくはないですね。。。
私は、福岡市在住ですが、その時間寝ていて、突然アラーム音で目が覚めました。そして『なんの音?』と寝ぼけながら考えようと思った瞬間に、家が揺れ始めました。揺れは数十秒で収まりましたが、このレベルの揺れは、6年前のこの時期(3月)に発生した福岡県西方沖地震以来でした。当時のほうが揺れはひどかったですけどね。
その後の報道で、軽傷者は出た模様ですが大きな被害ななくてホッとしています。一方、今回初めての経験だったのが「緊急地震速報」の受信でした。
そうです、あのアラーム音は、私のスマホが受信した「緊急地震速報」だったのです。ドコモによると(私のスマホはソフトバンクですが、、、)
緊急地震速報は、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に素早くお知らせするものです。
ドコモでは、気象庁から配信された 「一般向け緊急地震速報」を利用して最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)の地域(全国を約200の地域に区分)の携帯電話に一斉配信いたします。
とあります。寝ぼけていたので、記憶が曖昧ですが、私の場合、アラーム音で目が覚めてすぐに揺れが始まったのではないかと思います。
また、緊急地震速報を受信したということは、私が住んでいる場所で震度4以上を記録したということにもなります。
そんな揺れる直前に警報が届いても、、、とお考えの方もいるかもしれませんが、今回の経験から「ギリギリでも緊急速報」を受信したほうが、その後の対応にはいいのではいかと思った次第です。
少なくとも、寝た状態より、目覚めて意識があったほうが、室内での落下物への対応など、被害を回避する行動を取れる可能性が高いはずですもんね。
巨大地震の発生が噂される日本で、地震を避けること、事前に予測することは事実上不可能です。そのためには、地震が発生した場合の初期対応を如何に行うかが重要になってくると思います。そういった意味で、今回の緊急地震速報は、程度の差はあれどある一定の効果はあったのではないかと思いました。
まあ、あまり受信したくはないですね。。。
2014年03月04日
二日間のプチ断食
先週は、月曜日から日曜日まで、夜の会食が続きました。
お誘いは多いのですが、基本的に、
・仕事関係の会食
・気のおけない友との会食
について優先していて、半分以上のお誘いはお断りしているのですが、それでも先週は重なってしまいました。
料理は私のFBにアップしています。⇒こちら
他の週も、大体2−3回/週は外食の状況がここ1、2年続いていることもあり、体重もゆっくりとした右上がり傾向。今年に入りついに70キロを越えてしまいました。
ということで、一旦流れを変えようと、今日から明日までの二日間、プチ断食をします。
全く食べないということは、続かないし、体にも良くないので、朝・昼は、野菜ジュースやサラダ、ゆで卵にして、夕食はサラダ+一品にしようと思います。
二日間なので、体重が減ることを期待はしていませんが、習慣を変えたいというのが今回のプチ断食の趣旨です。
私と会っても、おやつなどは決して与えないでくださいね。
お誘いは多いのですが、基本的に、
・仕事関係の会食
・気のおけない友との会食
について優先していて、半分以上のお誘いはお断りしているのですが、それでも先週は重なってしまいました。
料理は私のFBにアップしています。⇒こちら
他の週も、大体2−3回/週は外食の状況がここ1、2年続いていることもあり、体重もゆっくりとした右上がり傾向。今年に入りついに70キロを越えてしまいました。
ということで、一旦流れを変えようと、今日から明日までの二日間、プチ断食をします。
全く食べないということは、続かないし、体にも良くないので、朝・昼は、野菜ジュースやサラダ、ゆで卵にして、夕食はサラダ+一品にしようと思います。
二日間なので、体重が減ることを期待はしていませんが、習慣を変えたいというのが今回のプチ断食の趣旨です。
私と会っても、おやつなどは決して与えないでくださいね。
タグ :プチ断食
2014年02月27日
博多天神
私は、仕事柄東京に出張することが多いのですが、その際に、新橋やお茶の水などいろんなところで見かけるのが、

「博多天神」というラーメン屋さんの看板です。
福岡在住者にとっては「笑ってしまう」ネーミングです。現在の福岡市は、元々「博多」という街と「福岡」という街が一緒になってできた都市です。
元々は、博多湾に面する現在の福岡市の中央部東側は、古来から博多(はかた)として認識されており、大陸方面への玄関口、今風にいうと「アジアへのゲートウェイ」として中世から貿易で栄えた商人の町です。
戦乱で度々焼き払われながらも、豊かな町人文化が育まれ、豊臣秀吉の手で復興されたあと、黒田家が福岡城とその城下町を築いたことで、那珂川(中洲を流れる川なのでご存知の方も多いと思います)を境に西が城下町としての「福岡」、東が商人町としての「博多」となったそうです。
そして、江戸時代から明治時代初めにかけて、福岡と博多は共存していましたが、1876年に福岡と博多は統合され福博(ふくはく)となり、その後、政府からの命により市制に移行する際に「福岡市」にするか「博多市」にするかで大論争が起こったそうです。
結果、勝ったのが「福岡市」という名称。それが現在の福岡市の原形となっています。
ちなみに、博多祇園山笠は、博多に伝わる祭りなので、基本的には那珂川の東側で行われます。
一方、天神とは、「福岡」の一番の繁華街の地名で、天神1−1−1には現在アクロス福岡という施設ができています。
その目の前にあるのが「水鏡天満宮」。太宰府に左遷されて博多にたどり着いた菅原道真公が、今泉辺りを流れていた四十川(現在の薬院新川)の水面に映った自身のやつれた姿を見て、嘆き悲しんだという言い伝えがあり、それにちなんで今泉に建てられた容見(すがたみ)天神が建てられました。
そして、現在NHK大河ドラマ「黒田官兵衛」で話題になっている福岡藩初代藩主・黒田長政によって水鏡天満宮として現在の地に移されたそうです。この天神様の移転が、現在の天神の地名の由来です。
ということで、福岡市民にとって「博多天神」というお店の名前は非常に違和感がある名前なんですよね。また、店員さんはほぼ全員外国の方なので、微妙な感じがしますが、個人的にはこのお店のラーメンは好きで、東京にあるそこいらの「博多ラーメン」を標榜するお店より「イケて」ますよ。私も何度か行ったことがあります。
博多天神、、、ブログを書いていると、次の出張時に立ち寄ってみたくなりました。

「博多天神」というラーメン屋さんの看板です。
福岡在住者にとっては「笑ってしまう」ネーミングです。現在の福岡市は、元々「博多」という街と「福岡」という街が一緒になってできた都市です。
元々は、博多湾に面する現在の福岡市の中央部東側は、古来から博多(はかた)として認識されており、大陸方面への玄関口、今風にいうと「アジアへのゲートウェイ」として中世から貿易で栄えた商人の町です。
戦乱で度々焼き払われながらも、豊かな町人文化が育まれ、豊臣秀吉の手で復興されたあと、黒田家が福岡城とその城下町を築いたことで、那珂川(中洲を流れる川なのでご存知の方も多いと思います)を境に西が城下町としての「福岡」、東が商人町としての「博多」となったそうです。
そして、江戸時代から明治時代初めにかけて、福岡と博多は共存していましたが、1876年に福岡と博多は統合され福博(ふくはく)となり、その後、政府からの命により市制に移行する際に「福岡市」にするか「博多市」にするかで大論争が起こったそうです。
結果、勝ったのが「福岡市」という名称。それが現在の福岡市の原形となっています。
ちなみに、博多祇園山笠は、博多に伝わる祭りなので、基本的には那珂川の東側で行われます。
一方、天神とは、「福岡」の一番の繁華街の地名で、天神1−1−1には現在アクロス福岡という施設ができています。
その目の前にあるのが「水鏡天満宮」。太宰府に左遷されて博多にたどり着いた菅原道真公が、今泉辺りを流れていた四十川(現在の薬院新川)の水面に映った自身のやつれた姿を見て、嘆き悲しんだという言い伝えがあり、それにちなんで今泉に建てられた容見(すがたみ)天神が建てられました。
そして、現在NHK大河ドラマ「黒田官兵衛」で話題になっている福岡藩初代藩主・黒田長政によって水鏡天満宮として現在の地に移されたそうです。この天神様の移転が、現在の天神の地名の由来です。
ということで、福岡市民にとって「博多天神」というお店の名前は非常に違和感がある名前なんですよね。また、店員さんはほぼ全員外国の方なので、微妙な感じがしますが、個人的にはこのお店のラーメンは好きで、東京にあるそこいらの「博多ラーメン」を標榜するお店より「イケて」ますよ。私も何度か行ったことがあります。
博多天神、、、ブログを書いていると、次の出張時に立ち寄ってみたくなりました。
2014年02月20日
久留米のソウルフード(ホットドッグ編)
本日は、東京へ日帰り出張です。
いつもどおり福岡空港に到着した後、朝ご飯を買おうと1Fの売店に寄ってみると、目に入ってきたのが、

「キムラヤのホットドッグ」です。
ご存知でない方もいらっしゃると思いますが、私の地元である久留米市のソウルフードの一つです。
荒木町の隣町である津福本町に株式会社木村屋のパン工場があり、売店が併設されています。そのお店に、子供の頃、小頭町公園の近くにあった塾「全教研」の行き帰りによく立ち寄り、買い食いしていました。ちなみに、

昨年末に北海道でお会いしたホリエモンこと堀江さんも小学生の頃から全教研に通っていたそうです。
久留米は、松田聖子先輩やチェッカーズ、ARBにシーナ&ザ・ロケッツなどミュージシャンや芸能人が多いですが、そのほとんどがこの「ホットドッグ」を食べたことがあると思います。このホットドッグの特徴は、具が「ウインナー」ではないということです。

なぜだか、昔ながらの赤耳プレスハムに刻みキャベツ。
ここが久留米の面白いところです。物の本によると、戦後まもなく、アメリカでは「ホットドッグ」という食べ物があると聞いた創業者の方が、ホットドッグという名前から「暑がっている犬」というふうに勝手に連想し、犬が暑くてハーハー息をしている姿をイメージし、プレスハムの赤い耳の部分をパンからはみ出させ、出来上がったのがこの「ホットドッグ」なのです。
なんだか訳が分からない感じもしますが(笑)、とんこつラーメンや黒棒、そしてこのホットドッグなど、独自の発想で新しいモノを生み出した先輩方を誇りに思います。
けど、現地だと170円くらいなのが、空港では200円。。。ちょっと高いかな?
ご興味がある方は、是非試してみてください。
いつもどおり福岡空港に到着した後、朝ご飯を買おうと1Fの売店に寄ってみると、目に入ってきたのが、

「キムラヤのホットドッグ」です。
ご存知でない方もいらっしゃると思いますが、私の地元である久留米市のソウルフードの一つです。
荒木町の隣町である津福本町に株式会社木村屋のパン工場があり、売店が併設されています。そのお店に、子供の頃、小頭町公園の近くにあった塾「全教研」の行き帰りによく立ち寄り、買い食いしていました。ちなみに、

昨年末に北海道でお会いしたホリエモンこと堀江さんも小学生の頃から全教研に通っていたそうです。
久留米は、松田聖子先輩やチェッカーズ、ARBにシーナ&ザ・ロケッツなどミュージシャンや芸能人が多いですが、そのほとんどがこの「ホットドッグ」を食べたことがあると思います。このホットドッグの特徴は、具が「ウインナー」ではないということです。

なぜだか、昔ながらの赤耳プレスハムに刻みキャベツ。
ここが久留米の面白いところです。物の本によると、戦後まもなく、アメリカでは「ホットドッグ」という食べ物があると聞いた創業者の方が、ホットドッグという名前から「暑がっている犬」というふうに勝手に連想し、犬が暑くてハーハー息をしている姿をイメージし、プレスハムの赤い耳の部分をパンからはみ出させ、出来上がったのがこの「ホットドッグ」なのです。
なんだか訳が分からない感じもしますが(笑)、とんこつラーメンや黒棒、そしてこのホットドッグなど、独自の発想で新しいモノを生み出した先輩方を誇りに思います。
けど、現地だと170円くらいなのが、空港では200円。。。ちょっと高いかな?
ご興味がある方は、是非試してみてください。
2014年02月19日
クレジットカード紛失騒動とポカヨケの発想
昨日、の昼に某銀行のATMでお金を引き出そうと財布からカードを取り出した際に、なんとなく違和感を感じました。

そこで気付いたのが、メインで使っている「ANA SUPER FLYERS CARD(以下、カード)」が見当たらないということです。
あれ?と思い、財布の他のポケットを確認しても見つかりません。そのあたりから段々焦ってきて、財布の紙幣や他のカードを全て取り出して確認しても見つかりません。
「いつカードを使ったかな?」と思い出してみると、前日の夕方、今週出張用の航空便の購入手続きをネットで行っていて、いつもカード決裁しているので、その際にカードを取り出したことに気付き、事務所に戻り机の上を確認しても見つかりません。
「、カードを使ったのは事務所ではなく、自宅だったけ?」と自宅の妻に電話してテーブルの上などを確認してみても見つかりませんでした。
うーん、困ったなと、他にカードを使った場所がないか頭をひねっても思い出せず、明日カード会社に電話してカード使用をストップさせなければと思った矢先に、妻から電話がありました。
前日夜に妻と娘と南福岡駅で合流し、車で自宅に戻る途中にガソリンスタンド(セルフ)に立寄り、灯油を1カン買ったのですが、その際にカード使ったんじゃない?って
それを聞いてようやく思い出しました。ちょうど雨が降っていて、灯油を給油し終わったあと、急いで車に戻ったのですが、その際に給油装置からカードを抜き取らずに車に戻ったんじゃないかなと。確かにカードを抜き取った記憶がありませんでした。至急妻にそのガソリンスタンドに電話をしてもらったら、、、ありました!
いやー、本当にホッとしました。普段車にガソリンを給油する際に、カードを使うのですが、いつも利用するセルフのガソリンスタンドの給油装置は、カードを挿入すると、認証が終わったあとすぐカードが戻ってきて、それから給油を開始するので、カードを取り忘れることはありません。
一方、前日に利用したガソリンスタンドの給油装置は、給油が終わったあとにカードが戻ってくるタイプのものでした。それに加え、雨が降っていて寒かったので、急いで車に戻ったので、思わず抜き取ることを忘れてしまったんですね。
妻によると、そのガソリンスタンドでは、カードの抜き忘れが多く、たくさんのカードをスタンドで預かっているそうです。そして、取りにくる人はほとんどいないそうです。。。
そこで思い出したのが、エンジニア時代に学んだ「ポカヨケ」の発想。
ポカヨケとは、工場などの製造ラインに設置される作業ミスを防止するための仕組みのことです。
どんな人でも作業ミスなどはやってしまうので、極力そういった「ポカ」(囲碁、将棋で用いられる用語で、通常は考えられない悪い手を打つ事を意味するそうです)を避ける(ヨケる)ための仕組みや発想を作業の中に取り入れることにより作業ミスを減らすのです。
今回のケースでも、雨が降っていて寒かったので、給油後急いで車に戻ったことがカードを抜き忘れる原因になったと考えられますが、給油の前に必ずカードが戻ってくるような給油装置であれば、カードを抜き取らないと給油ができないので、カードを取り忘れることはなかったと思います。
まあ「自己責任」なので、忘れた私が一番悪いのですが(笑)、私がカードを忘れたガソリンスタンドに多くのカードが抜き忘れにより保管してあることを知り、ちょっとブログに書きたくなった次第です。とにもかくにも見つかってよかった!

そこで気付いたのが、メインで使っている「ANA SUPER FLYERS CARD(以下、カード)」が見当たらないということです。
あれ?と思い、財布の他のポケットを確認しても見つかりません。そのあたりから段々焦ってきて、財布の紙幣や他のカードを全て取り出して確認しても見つかりません。
「いつカードを使ったかな?」と思い出してみると、前日の夕方、今週出張用の航空便の購入手続きをネットで行っていて、いつもカード決裁しているので、その際にカードを取り出したことに気付き、事務所に戻り机の上を確認しても見つかりません。
「、カードを使ったのは事務所ではなく、自宅だったけ?」と自宅の妻に電話してテーブルの上などを確認してみても見つかりませんでした。
うーん、困ったなと、他にカードを使った場所がないか頭をひねっても思い出せず、明日カード会社に電話してカード使用をストップさせなければと思った矢先に、妻から電話がありました。
前日夜に妻と娘と南福岡駅で合流し、車で自宅に戻る途中にガソリンスタンド(セルフ)に立寄り、灯油を1カン買ったのですが、その際にカード使ったんじゃない?って
それを聞いてようやく思い出しました。ちょうど雨が降っていて、灯油を給油し終わったあと、急いで車に戻ったのですが、その際に給油装置からカードを抜き取らずに車に戻ったんじゃないかなと。確かにカードを抜き取った記憶がありませんでした。至急妻にそのガソリンスタンドに電話をしてもらったら、、、ありました!
いやー、本当にホッとしました。普段車にガソリンを給油する際に、カードを使うのですが、いつも利用するセルフのガソリンスタンドの給油装置は、カードを挿入すると、認証が終わったあとすぐカードが戻ってきて、それから給油を開始するので、カードを取り忘れることはありません。
一方、前日に利用したガソリンスタンドの給油装置は、給油が終わったあとにカードが戻ってくるタイプのものでした。それに加え、雨が降っていて寒かったので、急いで車に戻ったので、思わず抜き取ることを忘れてしまったんですね。
妻によると、そのガソリンスタンドでは、カードの抜き忘れが多く、たくさんのカードをスタンドで預かっているそうです。そして、取りにくる人はほとんどいないそうです。。。
そこで思い出したのが、エンジニア時代に学んだ「ポカヨケ」の発想。
ポカヨケとは、工場などの製造ラインに設置される作業ミスを防止するための仕組みのことです。
どんな人でも作業ミスなどはやってしまうので、極力そういった「ポカ」(囲碁、将棋で用いられる用語で、通常は考えられない悪い手を打つ事を意味するそうです)を避ける(ヨケる)ための仕組みや発想を作業の中に取り入れることにより作業ミスを減らすのです。
今回のケースでも、雨が降っていて寒かったので、給油後急いで車に戻ったことがカードを抜き忘れる原因になったと考えられますが、給油の前に必ずカードが戻ってくるような給油装置であれば、カードを抜き取らないと給油ができないので、カードを取り忘れることはなかったと思います。
まあ「自己責任」なので、忘れた私が一番悪いのですが(笑)、私がカードを忘れたガソリンスタンドに多くのカードが抜き忘れにより保管してあることを知り、ちょっとブログに書きたくなった次第です。とにもかくにも見つかってよかった!
2014年02月05日
東アジア初「Google RISE Awards 」(Life is Tech編)
今日、なにげにFBのタイムラインを眺めていたら、嬉しいニュースを見つけました。
「この度、Life is Tech!は東アジア初の “Google RISE Awards ” に選ばれました!!」というコメントです。
Life is Techとは、若い起業家たちが設立したライフイズテック(株)が提供しているプログラムで、
春夏冬休み中など長期に休みの間に約一週間のキャンプを国内の有力大学のキャンパス(またはその近辺)で開催します。
どういったキャンプかというと、
主な対象は中学生・高校生 で、iPhoneアプリの開発やゲームデザイン・プログラミングなどの最新IT技術を、大学生のインストラクター・メンターが張り付いて教えながら学ぶことが出来るプログラムです。
なので、プログラミングやデザインが好きな学生はもちろんのこと、パソコンやスマートフォンをほとんど触ったことのない人でも、誰でも参加・技術習得ができて、「楽しく」「自主的に」「自然と」学ぶことができるプログラムです。
Google RISE Awardsとは、世界中でコンピューターサイエンスやICT教育の普及に貢献している組織に与えられる賞みたいで、今回「Life is Tech」が東アジアで初めて受賞したとのことです。⇒こちら
HPのとおり、九大でも開催され、九大の学生もインストラクターとしてこのプログラムにも参加しているのですが、私は、初めて九大で開催するにあたり、引き受けていただく教員やメンターとしての学生等の紹介および、開催場所について相談を受け、アドバイスさせていただきました。
今回の受賞では、首都圏以外での地域(九州・関西・四国・北海道etc)での講座開催が評価されたということで、そのキッカケの一端を担うことができ非常に嬉しい限りです。
今後、このプログラムが発展し、素晴らしい人材が日本中から次々と生まれることを期待しています。とにもかくにもおめでとうございます!
「この度、Life is Tech!は東アジア初の “Google RISE Awards ” に選ばれました!!」というコメントです。
Life is Techとは、若い起業家たちが設立したライフイズテック(株)が提供しているプログラムで、
春夏冬休み中など長期に休みの間に約一週間のキャンプを国内の有力大学のキャンパス(またはその近辺)で開催します。
どういったキャンプかというと、
主な対象は中学生・高校生 で、iPhoneアプリの開発やゲームデザイン・プログラミングなどの最新IT技術を、大学生のインストラクター・メンターが張り付いて教えながら学ぶことが出来るプログラムです。
なので、プログラミングやデザインが好きな学生はもちろんのこと、パソコンやスマートフォンをほとんど触ったことのない人でも、誰でも参加・技術習得ができて、「楽しく」「自主的に」「自然と」学ぶことができるプログラムです。
Google RISE Awardsとは、世界中でコンピューターサイエンスやICT教育の普及に貢献している組織に与えられる賞みたいで、今回「Life is Tech」が東アジアで初めて受賞したとのことです。⇒こちら
HPのとおり、九大でも開催され、九大の学生もインストラクターとしてこのプログラムにも参加しているのですが、私は、初めて九大で開催するにあたり、引き受けていただく教員やメンターとしての学生等の紹介および、開催場所について相談を受け、アドバイスさせていただきました。
今回の受賞では、首都圏以外での地域(九州・関西・四国・北海道etc)での講座開催が評価されたということで、そのキッカケの一端を担うことができ非常に嬉しい限りです。
今後、このプログラムが発展し、素晴らしい人材が日本中から次々と生まれることを期待しています。とにもかくにもおめでとうございます!
タグ :life is Tech受賞
2014年02月03日
航空チケットが、、、アベノミクスの効果?
今年に入り、東京に数回出張しました。
その際に感じたのが「航空便が混んでいるなー」ということです。
●●委員会出席など、予定・時間が事前に分かっている場合は、早めに航空チケットを予約するのですが、アポイントがギリギリに決まった場合など、直前にチケットを購入することが多々あります。昨年まではそれでも座席を確保できたのですが、今年に入りそれが厳しくなりました。
私は「ANA派」なのですが、前回出張した際に、航空チケットの予約を忘れていて、前日にチケットを購入しようとwebにアクセスしてみるとその日の午前中の便はほぼ満席でした。「これはヤバい」とJALのwebを確認しても同じ状況。結局、スカイマーク便でギリギリなんとか座席を確保できました。
宿泊時のホテルもかなり混んでいますね。。。
同様なことを、同僚や知り合いの大学教員も言っていました。偶然中・高校の修学旅行などにぶつかったなどの影響もあるかもしれませんが、間違いなく、人・モノの動きは昨年に比べ増えていると思います。
人・モノが動けばお金が動く=景気上昇のサインと言われていますが、まさにその状況ではないかと思った次第です。
これもアベノミクスの効果?なのでしょうか。。。ということで、今週末の出張の航空チケットを早めに予約しました(笑)
その際に感じたのが「航空便が混んでいるなー」ということです。
●●委員会出席など、予定・時間が事前に分かっている場合は、早めに航空チケットを予約するのですが、アポイントがギリギリに決まった場合など、直前にチケットを購入することが多々あります。昨年まではそれでも座席を確保できたのですが、今年に入りそれが厳しくなりました。
私は「ANA派」なのですが、前回出張した際に、航空チケットの予約を忘れていて、前日にチケットを購入しようとwebにアクセスしてみるとその日の午前中の便はほぼ満席でした。「これはヤバい」とJALのwebを確認しても同じ状況。結局、スカイマーク便でギリギリなんとか座席を確保できました。
宿泊時のホテルもかなり混んでいますね。。。
同様なことを、同僚や知り合いの大学教員も言っていました。偶然中・高校の修学旅行などにぶつかったなどの影響もあるかもしれませんが、間違いなく、人・モノの動きは昨年に比べ増えていると思います。
人・モノが動けばお金が動く=景気上昇のサインと言われていますが、まさにその状況ではないかと思った次第です。
これもアベノミクスの効果?なのでしょうか。。。ということで、今週末の出張の航空チケットを早めに予約しました(笑)
2014年01月15日
マウスピースを作ってみた。
昨年、以前に抜けた奥歯(一番奥)の部分にインプラントを入れました。50代を目前にするといろいろ体の維持にお金がかかってしまいますね。
その際にお世話になっている歯医者さんからアドバイスをされたのが、マウスピースを作ってみては?
ということでした。先生の診断によると、奥歯の噛みしめる力が強く、寝てる間も歯ぎしりしているのではないか?とのことでした。
私自身、歯ぎしりをやっている意識はないし、妻に聞いてもそのような音は聞かないということですが、先生やネットの情報によると、ギシギシと音を出さなくても、寝ている間に奥歯に力が入っている人は結構いらっしゃるようで、私もそうではないかということでした。ということで出来上がったものが、

コレです。材質は入れ歯の歯茎部分の材料みたいです。
私にとって、このマウスピースの製作目的は上述のとおり、
・歯ぎしりの予防
・噛みしめ・くいしばりの予防
・被せものの保護
です。
人によっては、あごの関節痛や開口障害の緩和を目的としてマウスピースを作る方もいらっしゃるようです。
昨晩装着してみたのですが、相当「違和感」があります(笑)。先生からも「違和感があると思うけど、一週間頑張ると慣れると思うので、2、3日で諦めないでくださいね。」と言われましたが、うーん結構ハードルは高そうです。
とはいえ、インプラントや被せものをできるだけ長持ちさせるためには有効のようですし、肩こり予防にもなるようなので、この一週間頑張ってマウスピースを装着して寝たいと思います。頑張ろうっと。
その際にお世話になっている歯医者さんからアドバイスをされたのが、マウスピースを作ってみては?
ということでした。先生の診断によると、奥歯の噛みしめる力が強く、寝てる間も歯ぎしりしているのではないか?とのことでした。
私自身、歯ぎしりをやっている意識はないし、妻に聞いてもそのような音は聞かないということですが、先生やネットの情報によると、ギシギシと音を出さなくても、寝ている間に奥歯に力が入っている人は結構いらっしゃるようで、私もそうではないかということでした。ということで出来上がったものが、

コレです。材質は入れ歯の歯茎部分の材料みたいです。
私にとって、このマウスピースの製作目的は上述のとおり、
・歯ぎしりの予防
・噛みしめ・くいしばりの予防
・被せものの保護
です。
人によっては、あごの関節痛や開口障害の緩和を目的としてマウスピースを作る方もいらっしゃるようです。
昨晩装着してみたのですが、相当「違和感」があります(笑)。先生からも「違和感があると思うけど、一週間頑張ると慣れると思うので、2、3日で諦めないでくださいね。」と言われましたが、うーん結構ハードルは高そうです。
とはいえ、インプラントや被せものをできるだけ長持ちさせるためには有効のようですし、肩こり予防にもなるようなので、この一週間頑張ってマウスピースを装着して寝たいと思います。頑張ろうっと。
2014年01月03日
自分のブログで今年(昨年)を振り返る2013その2
なんだかんだと年末ドタバタしていたら、新年を迎えてしまいました。。。
ということで、これを書かないと前へ進めないので、自分のブログで今年(昨年)を振り返る2013の後半です(笑)
7月のトピッックは、なんと言っても「博多祇園山笠」に入ったことです。流れは東流で町は下東町です。知り合いの会計士の先生から薦められてというか、
半強制的に誘われました。東流は、山をかくのが速いことで有名です。昨年は数日しか参加できませんでしたが、今年は出来る限り参加したいと思っています。
また、月末には日頃から大変お世話になっている九大システム情報科学研究院の都甲教授の紫綬褒章受章記念祝賀会が開催されました。若輩ものながら本会の発起人を務めさせていただきました。
8月は、上旬に宮崎で開催された九州地域戦略会議の夏季セミナーに参加し、宮崎で養殖されたチョウザメの身を食べました。昨年末からそのチョウザメから採れたキャビアは販売され、反響を呼んでいます。
お盆休みには、家族で香港に旅行に行き、グルメ三昧の楽しい時間を過ごしました。たまには家族サービスをしないといけませんね。。。
9月には、オフィスを長年通った九大箱崎キャンパスから、九大知的財産本部(現:産学官連携本部)とともに百道浜の九大イノベーションプラザに移転しました。通勤状況が大幅に変わってしまったので、未だに通勤に慣れていませんね。
10月には、九大生産機械工学科出身ながらエンジニアではなく違った仕事に就いている有志の会「九大生産機械工学科の会」を太郎源で開催しました。今後メンバーを増やしていきたいと思っています。
11月は、地元久留米で開催された「筑後地区九大同窓会」に参加しました。そして、ご依頼により基調講演を務めさせていただきました。最年長の出席者が90歳というのには驚きました。今後、この会が発展することを期待しています。
12月は、QBSの恩師である永田晃也教授がセンター長を務める九州大学科学技術イノベーション政策教育研究センター(CSTIPS)が実施している科学技術イノベーション(STI)政策専修科目の一つ「地域イノベーション政策特論」で、一コマ担当してほしいというご依頼があり、久しぶりに教壇に立ちました。
準備する時間を作るのに苦労しましたが、講義のレジュメを作成するにあたり産学連携の実務を体系的にまとめるという点ではいい経験でした。
ということで、早足でしたが、今年(昨年)を振り返ってみました。今年は、午年ということで丙午生まれの私は年男です。
飛躍の年になるよう精進・努力していきたいと思っていますので、今後ともご支援・ご指導方よろしくお願いいたします。
ということで、これを書かないと前へ進めないので、自分のブログで今年(昨年)を振り返る2013の後半です(笑)
7月のトピッックは、なんと言っても「博多祇園山笠」に入ったことです。流れは東流で町は下東町です。知り合いの会計士の先生から薦められてというか、
半強制的に誘われました。東流は、山をかくのが速いことで有名です。昨年は数日しか参加できませんでしたが、今年は出来る限り参加したいと思っています。
また、月末には日頃から大変お世話になっている九大システム情報科学研究院の都甲教授の紫綬褒章受章記念祝賀会が開催されました。若輩ものながら本会の発起人を務めさせていただきました。
8月は、上旬に宮崎で開催された九州地域戦略会議の夏季セミナーに参加し、宮崎で養殖されたチョウザメの身を食べました。昨年末からそのチョウザメから採れたキャビアは販売され、反響を呼んでいます。
お盆休みには、家族で香港に旅行に行き、グルメ三昧の楽しい時間を過ごしました。たまには家族サービスをしないといけませんね。。。
9月には、オフィスを長年通った九大箱崎キャンパスから、九大知的財産本部(現:産学官連携本部)とともに百道浜の九大イノベーションプラザに移転しました。通勤状況が大幅に変わってしまったので、未だに通勤に慣れていませんね。
10月には、九大生産機械工学科出身ながらエンジニアではなく違った仕事に就いている有志の会「九大生産機械工学科の会」を太郎源で開催しました。今後メンバーを増やしていきたいと思っています。
11月は、地元久留米で開催された「筑後地区九大同窓会」に参加しました。そして、ご依頼により基調講演を務めさせていただきました。最年長の出席者が90歳というのには驚きました。今後、この会が発展することを期待しています。
12月は、QBSの恩師である永田晃也教授がセンター長を務める九州大学科学技術イノベーション政策教育研究センター(CSTIPS)が実施している科学技術イノベーション(STI)政策専修科目の一つ「地域イノベーション政策特論」で、一コマ担当してほしいというご依頼があり、久しぶりに教壇に立ちました。
準備する時間を作るのに苦労しましたが、講義のレジュメを作成するにあたり産学連携の実務を体系的にまとめるという点ではいい経験でした。
ということで、早足でしたが、今年(昨年)を振り返ってみました。今年は、午年ということで丙午生まれの私は年男です。
飛躍の年になるよう精進・努力していきたいと思っていますので、今後ともご支援・ご指導方よろしくお願いいたします。
2013年12月31日
自分のブログで今年を振り返る2013その1
ブログの更新が滞っていましたが、気がつくと大晦日になってしまいました。
今年は、久しぶりに久留米の実家で年越しを迎える予定です。その前に自宅の大掃除でドタバタしています。。。ということで、恒例の「自分のブログで今年を振り返る」をやりたいと思います。
今年のスタートはシンガポールからでした。家族で初め海外で年越しを過ごしました。宿泊したホテルがリトルインディアの近くだったので、アジアの熱気を感じた年始でした。
2月は、TEDxFukuokaが初めて開催されました。プレゼンターを紹介したこともあり参加させていただきました。
また、福岡ではコ・ワーキングスペースや工房、インキュベーション施設などクリエイティブ系やベンチャーにとって新しい風が吹いた1年でした。ということで博多図工室を訪問しました。博多図工室は来年から場所を中洲川端に移し更に活動を拡大されるようです。
私にとって衝撃的な事件が起きたのも2月です。購入したばかりのiPhone5がタクシーに踏まれました。しかし、ケースのお陰で事無きをえました。私のiPhoneケースは、スピーカー機能付きの「タクシーに踏まれても壊れないiPhoneケース」です(笑)。
3月には、ワクチンを接種していたにも関わらず、インフルエンザに感染してしまいました。一方、クリエイティブ福岡の関連で、きゃりーぱみゅぱみゅのライブを間近に観ることができました。プロフェッナルのパフォーマンスに感心したことを今でも覚えています。
4月は、QBS(九大ビジネススクール)関係で嬉しい再会がありました。数年前にQBS受験について相談を受けた方が、様々な困難を乗り越え今年入学されました。
また、昨年からお手伝いさせていただいている「九州大学地域政策デザイナー養成講座」を今年も事務局&チューターとしてサポートさせていただくことになりました。
5月には、LLGAのイベントに参加するために、久しぶりに西海岸(サンフランシスコ)に行きました。
この時期、九州各地を安倍総理が訪問され、友人・知人が総理大臣と一緒にパネルに参加したり、研究の説明をしたりしました。
6月は、ILC(国際リニアコライダー)の誘致のため設立されたILC唐津推進協議会の理事として研究会に参加しました。残念ながら誘致に関しては東北に分がある結果となりましたが、まだまだどうなるかわかりません。
そして6月29日には、このブログのアクセス数が80万アクセスを越えました。7年かかりましたが、今後とも継続し100万アクセスを目指したいと思っています。
ということで後半はまた別途。つづく
今年は、久しぶりに久留米の実家で年越しを迎える予定です。その前に自宅の大掃除でドタバタしています。。。ということで、恒例の「自分のブログで今年を振り返る」をやりたいと思います。
今年のスタートはシンガポールからでした。家族で初め海外で年越しを過ごしました。宿泊したホテルがリトルインディアの近くだったので、アジアの熱気を感じた年始でした。
2月は、TEDxFukuokaが初めて開催されました。プレゼンターを紹介したこともあり参加させていただきました。
また、福岡ではコ・ワーキングスペースや工房、インキュベーション施設などクリエイティブ系やベンチャーにとって新しい風が吹いた1年でした。ということで博多図工室を訪問しました。博多図工室は来年から場所を中洲川端に移し更に活動を拡大されるようです。
私にとって衝撃的な事件が起きたのも2月です。購入したばかりのiPhone5がタクシーに踏まれました。しかし、ケースのお陰で事無きをえました。私のiPhoneケースは、スピーカー機能付きの「タクシーに踏まれても壊れないiPhoneケース」です(笑)。
3月には、ワクチンを接種していたにも関わらず、インフルエンザに感染してしまいました。一方、クリエイティブ福岡の関連で、きゃりーぱみゅぱみゅのライブを間近に観ることができました。プロフェッナルのパフォーマンスに感心したことを今でも覚えています。
4月は、QBS(九大ビジネススクール)関係で嬉しい再会がありました。数年前にQBS受験について相談を受けた方が、様々な困難を乗り越え今年入学されました。
また、昨年からお手伝いさせていただいている「九州大学地域政策デザイナー養成講座」を今年も事務局&チューターとしてサポートさせていただくことになりました。
5月には、LLGAのイベントに参加するために、久しぶりに西海岸(サンフランシスコ)に行きました。
この時期、九州各地を安倍総理が訪問され、友人・知人が総理大臣と一緒にパネルに参加したり、研究の説明をしたりしました。
6月は、ILC(国際リニアコライダー)の誘致のため設立されたILC唐津推進協議会の理事として研究会に参加しました。残念ながら誘致に関しては東北に分がある結果となりましたが、まだまだどうなるかわかりません。
そして6月29日には、このブログのアクセス数が80万アクセスを越えました。7年かかりましたが、今後とも継続し100万アクセスを目指したいと思っています。
ということで後半はまた別途。つづく
2013年12月10日
山笠は7月だけではない(博多のソーシャルキャピタル編)
12月に入り忘年会シーズンが本格化してきましたね。
先週末土曜日は、今年からお世話になっている博多祇園山笠東流の下東町の忘年会でした。

場所は、奥の堂にある奥堂。博多の町家を改装したいかにも「山笠」らしい場所でした。今年はあまり山の行事に参加できなかったにも関わらずお誘い頂き、諸先輩方と交流させていただくことができました。ただ辛いのが、山笠関係の宴では料理は基本的に残さない、ということ。料理が余ったら新人が処理班として活動しなければなりません。ここのところ会食が続いている私としてはちと苦しい限りです。
翌日は、町内の餅つきに参加させていただきました。

みなさんは、山笠といえば7月1日〜15日までの約2週間だけ山を舁くだけだと思っている方が多いかもしれませんが、実は違うのです。
山笠は元々博多の町内行事であり、山笠に参加するということは、その町内にお世話になること、と面接の際に総代から言われました。
つまり、年間通して町内行事やその他の山笠関係の行事には町内の住民のみなさんと同じ立場で参加するということなのです。特に山の「舁き手」(かきて)は、積極的に参加することが求められます。

朝、メンバーで集合して公民館に行ってみると、老若男女問わず地域の住民の方が多数集まり、ワイワイガヤガヤ餅つきをやっていました。こういった年代を越えた交流が博多の町できちんと行われていることは、本当に素晴らしいと感じました。

餅米は、消防団の方の監修のもと、地域の男衆が、なっ、なんと薪釜で蒸していました。
こういった地道な活動が、博多のソーシャル・キャピタルを生み出していて、その一番目立つ行事が「博多祇園山笠」だと思った次第です。
ということで、

私も、杵を持って餅つきに参加。想像以上に腕力と握力が必要なんですよね。3日経った今でも腕が凝っています(笑)。

けど、自分でついた餅は美味しかったですよ。なかなか忙しくて全ての町内行事に参加することは難しいですが、時間の許す限り積極的に参加しようと思っています。
といいながら、あと半年もすると山笠の季節がやってきます。月日が経つのは早いものですね。
先週末土曜日は、今年からお世話になっている博多祇園山笠東流の下東町の忘年会でした。

場所は、奥の堂にある奥堂。博多の町家を改装したいかにも「山笠」らしい場所でした。今年はあまり山の行事に参加できなかったにも関わらずお誘い頂き、諸先輩方と交流させていただくことができました。ただ辛いのが、山笠関係の宴では料理は基本的に残さない、ということ。料理が余ったら新人が処理班として活動しなければなりません。ここのところ会食が続いている私としてはちと苦しい限りです。
翌日は、町内の餅つきに参加させていただきました。

みなさんは、山笠といえば7月1日〜15日までの約2週間だけ山を舁くだけだと思っている方が多いかもしれませんが、実は違うのです。
山笠は元々博多の町内行事であり、山笠に参加するということは、その町内にお世話になること、と面接の際に総代から言われました。
つまり、年間通して町内行事やその他の山笠関係の行事には町内の住民のみなさんと同じ立場で参加するということなのです。特に山の「舁き手」(かきて)は、積極的に参加することが求められます。

朝、メンバーで集合して公民館に行ってみると、老若男女問わず地域の住民の方が多数集まり、ワイワイガヤガヤ餅つきをやっていました。こういった年代を越えた交流が博多の町できちんと行われていることは、本当に素晴らしいと感じました。

餅米は、消防団の方の監修のもと、地域の男衆が、なっ、なんと薪釜で蒸していました。
こういった地道な活動が、博多のソーシャル・キャピタルを生み出していて、その一番目立つ行事が「博多祇園山笠」だと思った次第です。
ということで、

私も、杵を持って餅つきに参加。想像以上に腕力と握力が必要なんですよね。3日経った今でも腕が凝っています(笑)。

けど、自分でついた餅は美味しかったですよ。なかなか忙しくて全ての町内行事に参加することは難しいですが、時間の許す限り積極的に参加しようと思っています。
といいながら、あと半年もすると山笠の季節がやってきます。月日が経つのは早いものですね。
2013年11月15日
サザエさん通りハッピーウエディング事業(百道浜交流会編)
昨日は、百道浜交流会に参加しました。

この交流会は、百道浜地区に拠点を置く企業の交流を目的として9年前にスタートしたそうです。年に一回開催されており、今回で9回目の開催です。
産学連携機構九州も、九大の産学連携部門とともに9月に百道浜に引っ越ししてきたということもあり、参加させていただきました。

この交流会の仕掛人がホークスタウンの右田会長です。実は、私の高校の大先輩であり、今回も右田先輩にお誘いいただき参加させていただいた次第です。
40〜50名が参加されており、大手IT企業、放送局、病院、百道浜地区の整備に関する指定管理者など、業種は多彩でした。
早良区の区長さんも参加されていたのすが、交流会用の配布資料の中で目に止まったが、
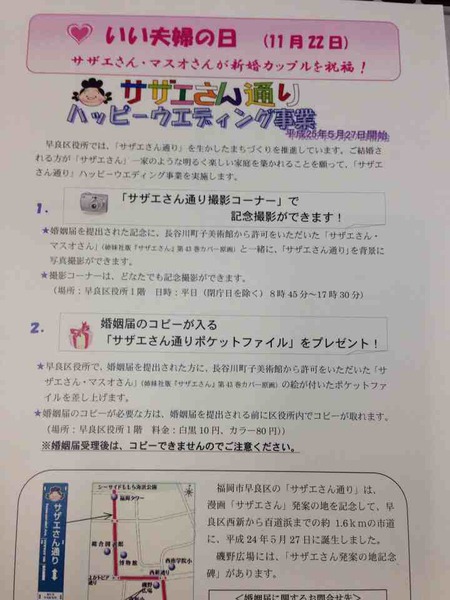
早良区がこのたび実施される「サザエさん通り ハッピーウエディング事業」のチラシでした。
詳細はこちら
11月22日は「いい夫婦の日」とは何となく知っていましたが、サザエさんの誕生日とは知りませんでした。
しかし、なぜ、早良区百道浜で「サザエさん」??? と思われる方がいらっしゃるかもしれませんね。
原作者である長谷川町子先生は九州出身(佐賀・福岡)で、百道の浜を歩きながら漫画「サザエさん」を発案したという逸話があり、平成24年には百道浜に「サザエさん通り」が誕生しています。
チラシによると、この事業に参加された方は、長谷川町子美術館から許可をいただいた「サザエさん・マスオさん」の原画と一緒に「サザエさん通り」を背景に写真撮影ができます。
また、早良区役所で婚姻届を提出した方は、長谷川町子美術館から許可を受けた「サザエさん・マスオさん」の絵が付いたポケットファイルを受け取ることができます。
この事業は本年5月27日から開始していますので、現在、直近のご予定があり、ご興味がある方は参加してみてはいかがでしょうか。
11月22日(いい夫婦の日)には、早良区役所1階の「サザエさん通り記念撮影コーナー」にサザエさん夫婦が登場するみたいですよ。

この交流会は、百道浜地区に拠点を置く企業の交流を目的として9年前にスタートしたそうです。年に一回開催されており、今回で9回目の開催です。
産学連携機構九州も、九大の産学連携部門とともに9月に百道浜に引っ越ししてきたということもあり、参加させていただきました。

この交流会の仕掛人がホークスタウンの右田会長です。実は、私の高校の大先輩であり、今回も右田先輩にお誘いいただき参加させていただいた次第です。
40〜50名が参加されており、大手IT企業、放送局、病院、百道浜地区の整備に関する指定管理者など、業種は多彩でした。
早良区の区長さんも参加されていたのすが、交流会用の配布資料の中で目に止まったが、
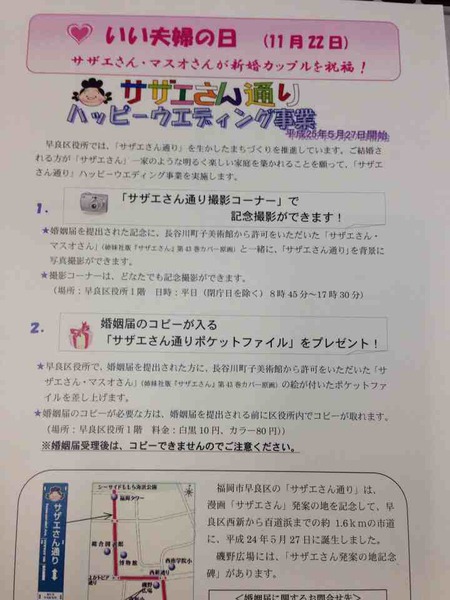
早良区がこのたび実施される「サザエさん通り ハッピーウエディング事業」のチラシでした。
詳細はこちら
11月22日は「いい夫婦の日」とは何となく知っていましたが、サザエさんの誕生日とは知りませんでした。
しかし、なぜ、早良区百道浜で「サザエさん」??? と思われる方がいらっしゃるかもしれませんね。
原作者である長谷川町子先生は九州出身(佐賀・福岡)で、百道の浜を歩きながら漫画「サザエさん」を発案したという逸話があり、平成24年には百道浜に「サザエさん通り」が誕生しています。
チラシによると、この事業に参加された方は、長谷川町子美術館から許可をいただいた「サザエさん・マスオさん」の原画と一緒に「サザエさん通り」を背景に写真撮影ができます。
また、早良区役所で婚姻届を提出した方は、長谷川町子美術館から許可を受けた「サザエさん・マスオさん」の絵が付いたポケットファイルを受け取ることができます。
この事業は本年5月27日から開始していますので、現在、直近のご予定があり、ご興味がある方は参加してみてはいかがでしょうか。
11月22日(いい夫婦の日)には、早良区役所1階の「サザエさん通り記念撮影コーナー」にサザエさん夫婦が登場するみたいですよ。
2013年11月11日
九州は「一つ」か「一つずつ」か?
先週末の11月9日(土)は、大学改革シンポジウム「社会の課題解決と大学教育・研究の融合」と合わせて、今年度もチューターを務めた九州大学地域政策デザイナー養成講座の政策提言発表会が開催されました。
「人口減少下の新たな成長のかたち」~ 現下の国際情勢と九州のビジネス戦略 ~
という大テーマのもと、
① 九州発・新国富論
② 地域の国際ビジネス戦略
③ 新たな官民連携
といった具体的なテーマについて、学生・社会人がチームを編成し、約半年にわたる講座・ワークショップおよび自主的な勉強会を経て提言をまとめました。

発表会の詳細はここでは述べませんが、この講座に参加した全ての方に、お疲れさまでした、と言いたいですね。特に社会人の方は、仕事を抱えながらプライベートの時間の多くを提言とりまとめのために費やされたのではないでしょうか。その努力に敬意を表したいと思います。
一方、このような提言にあたり、いつも強調されるのが「九州は一つ」ということです。
道州制の話題になると、真っ先にその実施候補地に挙がるのが「九州」です。では、本当に九州は一つなのでしょうか?
今回の提言の中に、九州が一体となり農産物の移出を支援する地域商社の創出といったプランがありました。プレゼン後の質疑応答では、今迄にも様々な提言が行われてきたにも関わらず、各県同士の思惑の相違によりなかなか連携がうまくいっていないとのコメントがありました。
イチゴを例にとると、福岡県には「あまおう」という有名なブランドイチゴがあります。一方、佐賀県は「さがほのか」といったブランドイチゴを開発し、県内の生産者の育成に力を入れています。それらを「統一ブランド」にして海外に移出するのはなかなか難しいものがあるということは容易に推測できます。
それに対し、香港など海外のマーケットからは、九州の農産物を売り込みたいのならば「窓口の一本化」「九州一体となったブランド」の提案をしてほしいという要望が挙がっているようです。相手は、ビジネスにおいて九州を「一つ」にしてほしいと思っているのです。
また、九州は一つといいながら、各地域・県ごとに言葉や文化はそれぞれで「一つずつ」です。
九州だとお酒は焼酎というイメージがあるかもしれませんが、北部九州は日本酒文化で南部九州(鹿児島、宮崎)は焼酎。特に久留米市城島は、日本酒の三大酒蔵と言われています。
ラーメンも博多(長浜)、久留米、熊本、鹿児島と同じとんこつでも全く別ものです。タテの話ばかりしていますが、ヨコの大分、長崎、佐賀も、それぞれ素晴らしい農産物、食材、文化があります。
私は福岡市に住んでいますが、鹿児島や宮崎には、今まで数回した行ったことがありません。むしろ、東京や大阪のほうが知人も多いし、親近感がわきます。熊本とはなぜだか友人・知人の繋がりが深いのですが、歴史的にみると、熊本と福岡は「九大」の誘致合戦などのこともあり、あくまでも個人的な意見ですが、自治体同士であまりいい関係にあるとは感じません。
といった具合に、九州に住んでいると、九州が一つといった感覚はほどんどないのが現実なのです。しかしながら、人口減少が始まっている日本において、地域の発展・成長を考えるのであれば「九州を一体化」していくことも非常に重要なポイントといえます。
九州は「一つ」なのか「一つずつ」なのか、本当に深い話です。
「人口減少下の新たな成長のかたち」~ 現下の国際情勢と九州のビジネス戦略 ~
という大テーマのもと、
① 九州発・新国富論
② 地域の国際ビジネス戦略
③ 新たな官民連携
といった具体的なテーマについて、学生・社会人がチームを編成し、約半年にわたる講座・ワークショップおよび自主的な勉強会を経て提言をまとめました。

発表会の詳細はここでは述べませんが、この講座に参加した全ての方に、お疲れさまでした、と言いたいですね。特に社会人の方は、仕事を抱えながらプライベートの時間の多くを提言とりまとめのために費やされたのではないでしょうか。その努力に敬意を表したいと思います。
一方、このような提言にあたり、いつも強調されるのが「九州は一つ」ということです。
道州制の話題になると、真っ先にその実施候補地に挙がるのが「九州」です。では、本当に九州は一つなのでしょうか?
今回の提言の中に、九州が一体となり農産物の移出を支援する地域商社の創出といったプランがありました。プレゼン後の質疑応答では、今迄にも様々な提言が行われてきたにも関わらず、各県同士の思惑の相違によりなかなか連携がうまくいっていないとのコメントがありました。
イチゴを例にとると、福岡県には「あまおう」という有名なブランドイチゴがあります。一方、佐賀県は「さがほのか」といったブランドイチゴを開発し、県内の生産者の育成に力を入れています。それらを「統一ブランド」にして海外に移出するのはなかなか難しいものがあるということは容易に推測できます。
それに対し、香港など海外のマーケットからは、九州の農産物を売り込みたいのならば「窓口の一本化」「九州一体となったブランド」の提案をしてほしいという要望が挙がっているようです。相手は、ビジネスにおいて九州を「一つ」にしてほしいと思っているのです。
また、九州は一つといいながら、各地域・県ごとに言葉や文化はそれぞれで「一つずつ」です。
九州だとお酒は焼酎というイメージがあるかもしれませんが、北部九州は日本酒文化で南部九州(鹿児島、宮崎)は焼酎。特に久留米市城島は、日本酒の三大酒蔵と言われています。
ラーメンも博多(長浜)、久留米、熊本、鹿児島と同じとんこつでも全く別ものです。タテの話ばかりしていますが、ヨコの大分、長崎、佐賀も、それぞれ素晴らしい農産物、食材、文化があります。
私は福岡市に住んでいますが、鹿児島や宮崎には、今まで数回した行ったことがありません。むしろ、東京や大阪のほうが知人も多いし、親近感がわきます。熊本とはなぜだか友人・知人の繋がりが深いのですが、歴史的にみると、熊本と福岡は「九大」の誘致合戦などのこともあり、あくまでも個人的な意見ですが、自治体同士であまりいい関係にあるとは感じません。
といった具合に、九州に住んでいると、九州が一つといった感覚はほどんどないのが現実なのです。しかしながら、人口減少が始まっている日本において、地域の発展・成長を考えるのであれば「九州を一体化」していくことも非常に重要なポイントといえます。
九州は「一つ」なのか「一つずつ」なのか、本当に深い話です。
2013年11月01日
ファブラボ@三松オープン
先週末は、八女で友人の会社のゴルフコンペに参加させていただきました。会社の名前は「三松」

私のiPhoneケースを作っていただいた会社です。タクシーに踏まれても壊れないiPhoneケースとして有名なケースです(笑)。
元々板金加工から始まり、今では様々な機械加工や組立、ソフトウエアの開発等にも分野を拡げられています。
小ロット・多品種生産も特徴の一つです。
また、産学連携にも取り組まれていて、九大発ベンチャーである「リナシメタリ」とCREO(クレオ)金属加工熱処理技術で連携し、自社工場内に「RMAセンター」を開設していらっしゃいます。
そんな三松さんが、新しく立ち上げられたのが「三松ファブラボ」。先日来、お話は伺っていましたが、ようやく情報がオープンになりました。
巷では「Makers」「3Dプリンター」ブームですが、そのほとんどがホビーユースを対象としている印象を受けます。
一方、プロであるモノづくり系の中小企業は、旧来型の下請け生産がメインで、このような流れに乗って新たなビジネスチャンスを見つけるような動きをしている企業は、少なくとも九州地域では皆無ではないかと思います。
この空白地帯に目をつけただけ(アイデア段階)でなく、実行されたということが素晴らしいなーと思った次第です。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ファブラボ(Fab Lab)とは、Fabrication Laboratory (加工研究所)の略称。
個人ユーザーや大学・研究機関の研究者のアイデアを形にする場としてファブラボは活用されると思いますが、福岡のクリエーター系・IT関連の企業とコラボすると更に面白いことになるのではないかと勝手に想像しています。
とにもかくにも、福岡のモノづくりの現場からイノベーションが生まれることを期待しています。

私のiPhoneケースを作っていただいた会社です。タクシーに踏まれても壊れないiPhoneケースとして有名なケースです(笑)。
元々板金加工から始まり、今では様々な機械加工や組立、ソフトウエアの開発等にも分野を拡げられています。
小ロット・多品種生産も特徴の一つです。
また、産学連携にも取り組まれていて、九大発ベンチャーである「リナシメタリ」とCREO(クレオ)金属加工熱処理技術で連携し、自社工場内に「RMAセンター」を開設していらっしゃいます。
そんな三松さんが、新しく立ち上げられたのが「三松ファブラボ」。先日来、お話は伺っていましたが、ようやく情報がオープンになりました。
巷では「Makers」「3Dプリンター」ブームですが、そのほとんどがホビーユースを対象としている印象を受けます。
一方、プロであるモノづくり系の中小企業は、旧来型の下請け生産がメインで、このような流れに乗って新たなビジネスチャンスを見つけるような動きをしている企業は、少なくとも九州地域では皆無ではないかと思います。
この空白地帯に目をつけただけ(アイデア段階)でなく、実行されたということが素晴らしいなーと思った次第です。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ファブラボ(Fab Lab)とは、Fabrication Laboratory (加工研究所)の略称。
個人ユーザーや大学・研究機関の研究者のアイデアを形にする場としてファブラボは活用されると思いますが、福岡のクリエーター系・IT関連の企業とコラボすると更に面白いことになるのではないかと勝手に想像しています。
とにもかくにも、福岡のモノづくりの現場からイノベーションが生まれることを期待しています。
2013年10月30日
一隅を照らす(みずあかり編)
今日は、久しぶりに九州経済フォーラムの「早朝会」に参加させていただきました。
この早朝会は、地域の経済界の皆様が、朝食を摂りながら各界で活躍されている方の講演を聞くといった勉強会です。
今回のご講演者は、東光石油株式会社 代表取締役会長 石原靖也さん。演題は「『みずあかり』日本一の秘密」でした。

みなさん、「熊本暮らし人祭り みずあかり」というお祭りをご存知でしょうか?残念ながら私は勉強不足で知りませんでした。
公式HPによると、「みずあかり」とは、故郷・熊本の魅力を発見し、「ここに暮らす喜びや切なさまでも共感できる市民と地域でありたい」をコンセプトとして2004年に始まり、熊本城から続く桜町から花畑公園にかけて続くシンボルロードを5万4千個のろうそくが彩るお祭りです。
今年のお祭りについてはこちら
このお祭りを立ち上げたメンバーであり、みずあかり実行委員会 実行委員長を務めていらっしゃるのが石原さんなのです。
ここではこのお祭りをやろうとしたキッカケや逸話は取り上げませんが(公式HPに詳しく書かれていますので、そちらをご参照ください)、素晴らしいご講演でした。
中でも、心に残ったのが、「一隅を照らす」という言葉です。
このお祭りの特徴の一つが、
◯公に頼らない
ということです。石原さんによると、熊本の悪いところは、「ぶらさがり」。何かしようとすると、公(自治体など)・補助金を頼る、つまり、何かにぶらさがってばかりいるのが地域の問題点であるとおっしゃていました。このようなイベントを企画すると、自治体に金銭的な支援を受けるための相談に行くことが多いのですが、このお祭りは、全て民間のボランティア・市民(企業含む)からの寄付で成り立っているそうです。
今年は、のべ5000人のボランティアが準備や運営に参加され、期間中(10月12日ー13日)に約20万人の観光客が熊本を訪れたとのことです。
また、このお祭りに込めた思いは、
①ここに暮す人々に、これ以上のない故郷の「誇り」を抱いていただくこと。
②ここに暮す人々の「希望の灯り」となること。
③この地に暮す責任とこの地の豊かさに貢献する、「暮らし人(くらしびと)」となること。
ここででてくるのが「一隅を照らす」という言葉です。
この言葉は、天台宗を開いた伝教大師最澄が書いた『山家学生式』(さんげがくしょうしき)の冒頭にでてきます。
「径寸十枚是れ国宝に非ず、一隅を照らす此れ則ち国宝なり」
天台宗のHPによると、「径寸十枚」とは金銀財宝などのことで、「一隅」とは今自分がいる場所や置かれた立場を指すそうです。
「お金や財宝は国の宝ではなく、自分自身が置かれたその場所で、精一杯努力し、明るく光り輝くことのできる人こそが、何物にも代えがたい貴い国の宝である」と書かれています。
そして、一人ひとりがそれぞれの持ち場で最善を尽くすことによって、まず自分自身を照らし、そしてこれが自然に周囲の人々の心を打ち、響いていくことで他の人々も照らしていく、そうやってお互いに良い影響を与え合い、やがて社会全体が明るく照らされていく。。。
まさに、このお祭りは、ボランティア、寄付をされた個人、企業の方が、自分の立ち位置でできる最大限の努力をし、実行することで、それが大きなうねりとなり、素晴らしいお祭りに成長していったのではないかと思った次第です。
つまり、市民の皆さんがそれぞれの立場で「一隅を照らす」ことにより成り立っているのです。
何事もカッコいいこと、目立つことばかりをやってしまいがちですが、自分の立ち位置をキチンと認識し、今の自分にできることを黙々と、最大限努力すること、またそれを継続することが、結果として、会社や家庭、社会いい方向に持っていく近道なのだと改めて気付きました。
一隅を照らす、まずは、小さいことから始めてみたいと思います。
この早朝会は、地域の経済界の皆様が、朝食を摂りながら各界で活躍されている方の講演を聞くといった勉強会です。
今回のご講演者は、東光石油株式会社 代表取締役会長 石原靖也さん。演題は「『みずあかり』日本一の秘密」でした。

みなさん、「熊本暮らし人祭り みずあかり」というお祭りをご存知でしょうか?残念ながら私は勉強不足で知りませんでした。
公式HPによると、「みずあかり」とは、故郷・熊本の魅力を発見し、「ここに暮らす喜びや切なさまでも共感できる市民と地域でありたい」をコンセプトとして2004年に始まり、熊本城から続く桜町から花畑公園にかけて続くシンボルロードを5万4千個のろうそくが彩るお祭りです。
今年のお祭りについてはこちら
このお祭りを立ち上げたメンバーであり、みずあかり実行委員会 実行委員長を務めていらっしゃるのが石原さんなのです。
ここではこのお祭りをやろうとしたキッカケや逸話は取り上げませんが(公式HPに詳しく書かれていますので、そちらをご参照ください)、素晴らしいご講演でした。
中でも、心に残ったのが、「一隅を照らす」という言葉です。
このお祭りの特徴の一つが、
◯公に頼らない
ということです。石原さんによると、熊本の悪いところは、「ぶらさがり」。何かしようとすると、公(自治体など)・補助金を頼る、つまり、何かにぶらさがってばかりいるのが地域の問題点であるとおっしゃていました。このようなイベントを企画すると、自治体に金銭的な支援を受けるための相談に行くことが多いのですが、このお祭りは、全て民間のボランティア・市民(企業含む)からの寄付で成り立っているそうです。
今年は、のべ5000人のボランティアが準備や運営に参加され、期間中(10月12日ー13日)に約20万人の観光客が熊本を訪れたとのことです。
また、このお祭りに込めた思いは、
①ここに暮す人々に、これ以上のない故郷の「誇り」を抱いていただくこと。
②ここに暮す人々の「希望の灯り」となること。
③この地に暮す責任とこの地の豊かさに貢献する、「暮らし人(くらしびと)」となること。
ここででてくるのが「一隅を照らす」という言葉です。
この言葉は、天台宗を開いた伝教大師最澄が書いた『山家学生式』(さんげがくしょうしき)の冒頭にでてきます。
「径寸十枚是れ国宝に非ず、一隅を照らす此れ則ち国宝なり」
天台宗のHPによると、「径寸十枚」とは金銀財宝などのことで、「一隅」とは今自分がいる場所や置かれた立場を指すそうです。
「お金や財宝は国の宝ではなく、自分自身が置かれたその場所で、精一杯努力し、明るく光り輝くことのできる人こそが、何物にも代えがたい貴い国の宝である」と書かれています。
そして、一人ひとりがそれぞれの持ち場で最善を尽くすことによって、まず自分自身を照らし、そしてこれが自然に周囲の人々の心を打ち、響いていくことで他の人々も照らしていく、そうやってお互いに良い影響を与え合い、やがて社会全体が明るく照らされていく。。。
まさに、このお祭りは、ボランティア、寄付をされた個人、企業の方が、自分の立ち位置でできる最大限の努力をし、実行することで、それが大きなうねりとなり、素晴らしいお祭りに成長していったのではないかと思った次第です。
つまり、市民の皆さんがそれぞれの立場で「一隅を照らす」ことにより成り立っているのです。
何事もカッコいいこと、目立つことばかりをやってしまいがちですが、自分の立ち位置をキチンと認識し、今の自分にできることを黙々と、最大限努力すること、またそれを継続することが、結果として、会社や家庭、社会いい方向に持っていく近道なのだと改めて気付きました。
一隅を照らす、まずは、小さいことから始めてみたいと思います。
2013年10月25日
偽装か誤表示か、本質って何?
今朝のニュースでは、某ホテルチェーンの「偽装?誤表示」問題が画面を賑わしていましたね。
というか、オープン情報なのでそのまま記載しますが、阪急阪神ホテルズが、ホテルのレストランなどでメニュー表示と異なる食材を使用していた問題について、社長が記者会見をし、「信頼を裏切ったお客様に心よりおわび申し上げます」と謝罪した一方で、原因は「従業員の認識・知識不足にある」ということで、これは「偽装でなく誤表示」と強調されていました。
ニュースによると記者会見は約3時間にも及んだそうです。私もこのニュースを観ていて、ああいえば上祐的な社長の対応はどうなんだろうなと感じました。何か本質を間違っているのではないかと。
様々な食材についてメニューの表示と異なった食材が仕様されていたようですが、それは恣意的に偽装したわけではなく、例えば食材の仕入れ段階において仕様が変更になり、その変更がメニューの表示まで至らなかった情報共有の不足、従業員の方の認識不足が原因であり、偽装ではなく誤表示にあたるというのが会社側の主張でした。
なぜ、そこまで「偽装」ではなく「誤表示」にこだわられるのかが、私はよくわかりませんでした。
なぜならば、誤表示だとするならば、それはそれで会社の信用を落とすことになるからです。
例えば、レッドキャビアという表示に対して、とびこ(トビウオのタマゴを塩漬けしたもの)を使用していたという事例があったそうです。
とびこは、回転寿司の軍艦のネタによく使われる比較的安価な食材です。しかし、食のプロであれば、外見・味、仕入れ値ともにレッドキャビアと明らかにその違いは分かるはずです(私でもわかります)。それが分からずにシェフがこれらを使用していたとは考えにくいのではないでしょうか?
もし、そうであれば、明らかに偽装になると思います。しかし、会社はそうではなく情報共有不足や、従業員の認識不足に起因する誤表示だとおっしゃる。
そうであれば「そんなレベルの低いシェフ・スタッフ」が調理やレストランの経営に携わっていたということになります。そんな「とんでもないレストラン」に高いお金を払って行きたいと思う消費者がいるでしょうか?少なくとも、私はそんなレストランに行きたいと思いません。
しかしながらこの会社の経営者は、会見で偽装は認めなくても、「私のレストランは、レベルの低いシェフ・スタッフが運営しています」という事実を認めているのです。
会社側は、この会見で「偽装ではない」ということを論理立てて説明しようとしたあまり、本質を見失ってしまったのではないでしょうか。
いやはや、私もこのようなわけのわからない会見を観て、他山の石としなければと思った次第です。
というか、オープン情報なのでそのまま記載しますが、阪急阪神ホテルズが、ホテルのレストランなどでメニュー表示と異なる食材を使用していた問題について、社長が記者会見をし、「信頼を裏切ったお客様に心よりおわび申し上げます」と謝罪した一方で、原因は「従業員の認識・知識不足にある」ということで、これは「偽装でなく誤表示」と強調されていました。
ニュースによると記者会見は約3時間にも及んだそうです。私もこのニュースを観ていて、ああいえば上祐的な社長の対応はどうなんだろうなと感じました。何か本質を間違っているのではないかと。
様々な食材についてメニューの表示と異なった食材が仕様されていたようですが、それは恣意的に偽装したわけではなく、例えば食材の仕入れ段階において仕様が変更になり、その変更がメニューの表示まで至らなかった情報共有の不足、従業員の方の認識不足が原因であり、偽装ではなく誤表示にあたるというのが会社側の主張でした。
なぜ、そこまで「偽装」ではなく「誤表示」にこだわられるのかが、私はよくわかりませんでした。
なぜならば、誤表示だとするならば、それはそれで会社の信用を落とすことになるからです。
例えば、レッドキャビアという表示に対して、とびこ(トビウオのタマゴを塩漬けしたもの)を使用していたという事例があったそうです。
とびこは、回転寿司の軍艦のネタによく使われる比較的安価な食材です。しかし、食のプロであれば、外見・味、仕入れ値ともにレッドキャビアと明らかにその違いは分かるはずです(私でもわかります)。それが分からずにシェフがこれらを使用していたとは考えにくいのではないでしょうか?
もし、そうであれば、明らかに偽装になると思います。しかし、会社はそうではなく情報共有不足や、従業員の認識不足に起因する誤表示だとおっしゃる。
そうであれば「そんなレベルの低いシェフ・スタッフ」が調理やレストランの経営に携わっていたということになります。そんな「とんでもないレストラン」に高いお金を払って行きたいと思う消費者がいるでしょうか?少なくとも、私はそんなレストランに行きたいと思いません。
しかしながらこの会社の経営者は、会見で偽装は認めなくても、「私のレストランは、レベルの低いシェフ・スタッフが運営しています」という事実を認めているのです。
会社側は、この会見で「偽装ではない」ということを論理立てて説明しようとしたあまり、本質を見失ってしまったのではないでしょうか。
いやはや、私もこのようなわけのわからない会見を観て、他山の石としなければと思った次第です。
2013年10月24日
太平君と洋子ちゃん(西新駅編)
9月にオフィスが百道浜に移り、西新駅を利用する機会が増えました。
一昨日、西新駅からSAM会の会場であるOnRAMPに向かう途中に発見したのが、

太平君と洋子ちゃん。
平成元年(1989年)に福岡で開催されたアジア太平洋博覧会のマスコットです。ちなみにこのマスコットのデザインは手塚治虫先生が担当されました。
この博覧会の通称は、よかトピア。私が勤務する百道浜の辺りは、この博覧会の会場として利用され、その後開発された地域です。
平成元年は、私が大学を卒業した年。卒業前によかトピアに行ったこと、今でも覚えています。

いやはや24年前、若いですね。
色々調べてみると、この博覧会をキッカケにして「よかトピア記念国際財団」が創設され、
●福岡アジア文化賞
●アジア太平洋こども会議・イン福岡
といった取り組みについて助成をされています。これは知らなかったですね。
で、話は西新駅に戻ります。冒頭の写真の太平君と洋子ちゃんの下部に目を向けると、汚れが目立ちます。その原因は、明らかに壁画の下に見えるゴミ箱です。
しかも「博覧会のマスコットデザイン、、、」という文字が見えますが、これはマスコットの説明書きだと推察されます。その前にゴミ箱が置かれているため、説明を読むことができませんし、壁画が汚れる原因にもなっています。
福岡市の地下鉄は、福岡市営です。福岡市が、市制100周年の記念事業と実施したよかトピアの「メモリー」を福岡市営地下鉄が台無しにしているのは、なんなんだろうなーと思った次第です。
ゴミ箱を数メーターずらすだけ、なんとかできないかなーと思いながら地下鉄に飛び乗った博多の夕暮れでした。
一昨日、西新駅からSAM会の会場であるOnRAMPに向かう途中に発見したのが、

太平君と洋子ちゃん。
平成元年(1989年)に福岡で開催されたアジア太平洋博覧会のマスコットです。ちなみにこのマスコットのデザインは手塚治虫先生が担当されました。
この博覧会の通称は、よかトピア。私が勤務する百道浜の辺りは、この博覧会の会場として利用され、その後開発された地域です。
平成元年は、私が大学を卒業した年。卒業前によかトピアに行ったこと、今でも覚えています。

いやはや24年前、若いですね。
色々調べてみると、この博覧会をキッカケにして「よかトピア記念国際財団」が創設され、
●福岡アジア文化賞
●アジア太平洋こども会議・イン福岡
といった取り組みについて助成をされています。これは知らなかったですね。
で、話は西新駅に戻ります。冒頭の写真の太平君と洋子ちゃんの下部に目を向けると、汚れが目立ちます。その原因は、明らかに壁画の下に見えるゴミ箱です。
しかも「博覧会のマスコットデザイン、、、」という文字が見えますが、これはマスコットの説明書きだと推察されます。その前にゴミ箱が置かれているため、説明を読むことができませんし、壁画が汚れる原因にもなっています。
福岡市の地下鉄は、福岡市営です。福岡市が、市制100周年の記念事業と実施したよかトピアの「メモリー」を福岡市営地下鉄が台無しにしているのは、なんなんだろうなーと思った次第です。
ゴミ箱を数メーターずらすだけ、なんとかできないかなーと思いながら地下鉄に飛び乗った博多の夕暮れでした。
2013年10月17日
箱崎が遠くなりにけり
ブログでも書きましたが、産学連携機構九州のオフィスが、百道浜の九大産学官連携イノベーションプラザに移転して一ヶ月半が経ちました。
今週火曜日に、打ち合わせがあり久しぶりに箱崎キャンパスを訪れました。知的財産本部&産学連携機構九州合わせて約10年通った仕事場です。

よく考えたら学生時代より長くこのキャンパスに居たことになります。たった一ヶ月半しか経っていないのですが、すごく懐かしい感じがしました。ちょっと時間があったので、正門あたりを歩いてみると、

記念碑を発見しました。現在、人文学系の学科は貝塚キャンパスにありますのが、ずっと前には、正門のすぐちかくにある建物(旧:先導科学物質研究所)が、法文学部(今では法学部と文学部に分かれています)の校舎だったのです。
正門を出て、ちょっと歩いてみると、この一ヶ月半の間に、中華料理屋さんが、

焼鳥屋さんに変わっていました。
一方、

学生時代から見覚えがあるお店は、健在でした。スナック・モツ鍋というキャッチが印象的です(笑)。たった一ヶ月半なのですが、箱崎がすごく遠くに、懐かしい場所に感じた次第です。完全にキャンパスが移転したらどうなるんだろう?
今週火曜日に、打ち合わせがあり久しぶりに箱崎キャンパスを訪れました。知的財産本部&産学連携機構九州合わせて約10年通った仕事場です。

よく考えたら学生時代より長くこのキャンパスに居たことになります。たった一ヶ月半しか経っていないのですが、すごく懐かしい感じがしました。ちょっと時間があったので、正門あたりを歩いてみると、

記念碑を発見しました。現在、人文学系の学科は貝塚キャンパスにありますのが、ずっと前には、正門のすぐちかくにある建物(旧:先導科学物質研究所)が、法文学部(今では法学部と文学部に分かれています)の校舎だったのです。
正門を出て、ちょっと歩いてみると、この一ヶ月半の間に、中華料理屋さんが、

焼鳥屋さんに変わっていました。
一方、

学生時代から見覚えがあるお店は、健在でした。スナック・モツ鍋というキャッチが印象的です(笑)。たった一ヶ月半なのですが、箱崎がすごく遠くに、懐かしい場所に感じた次第です。完全にキャンパスが移転したらどうなるんだろう?
2013年09月10日
SUBWAY
9月に事務所が移転し、ランチの状況が色々変わりました。箱崎キャンパスではほとんどコンビニで購入した弁当やカップラーメン、おにぎりだったのですが、周りに飲食店が結構あるのでもう少し色々チャレンジしてみようと思っています。
その中で最近ハマっているのが、

「SUBWAY」です。以前は福岡であまり見かけませんでしたが、最近店舗が増えています。日本ではサントリーがエリアフランチャイザーのようですね。
SUBWAYのいいところは、全ての食材に「カロリー表示がされている」という点です。サンドだけでなく、トッピング食材、ソース、ドリンクにもカロリーが記載されています。私自身、なんだかんだとダイエットというよりは、体重をキープすることが主になっていますが、夜の会食が多いのでランチのカロリーは結構気にしています。
大体サンド1つで250〜400キロカロリーといったところでしょうか。

今日選択したのは日替わりサンドで、本日は「照り焼きチキン」でした。
追加トッピングについては、まだ要領をえていません。今日は照り焼きチキンだったのでタマゴを追加しましたが、悪いクセがでてついでにチーズもトッピングしてしまいました。正直言ってチーズは不要でしたね。。。
メニューは豊富で、トッピングの組み合わせ方法もかなりありますので、マクドナルドのようにマンネリ化することは当分ないようです。
まずは、飽きるまでちょくちょく行ってみようと思っています。
その中で最近ハマっているのが、

「SUBWAY」です。以前は福岡であまり見かけませんでしたが、最近店舗が増えています。日本ではサントリーがエリアフランチャイザーのようですね。
SUBWAYのいいところは、全ての食材に「カロリー表示がされている」という点です。サンドだけでなく、トッピング食材、ソース、ドリンクにもカロリーが記載されています。私自身、なんだかんだとダイエットというよりは、体重をキープすることが主になっていますが、夜の会食が多いのでランチのカロリーは結構気にしています。
大体サンド1つで250〜400キロカロリーといったところでしょうか。

今日選択したのは日替わりサンドで、本日は「照り焼きチキン」でした。
追加トッピングについては、まだ要領をえていません。今日は照り焼きチキンだったのでタマゴを追加しましたが、悪いクセがでてついでにチーズもトッピングしてしまいました。正直言ってチーズは不要でしたね。。。
メニューは豊富で、トッピングの組み合わせ方法もかなりありますので、マクドナルドのようにマンネリ化することは当分ないようです。
まずは、飽きるまでちょくちょく行ってみようと思っています。







